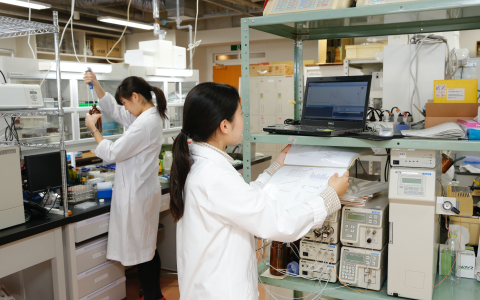「この一冊」 図書のご紹介


- 大学案内 About us
- 学部・大学院 Faculty Guide
-
入試情報
Exam Guide
- 大学機関 施設 University facilities
- 研究・産官学連携 Research and collaboration
- 学生生活 Student life
- 社会貢献・連携 Social Contribution and Cooperation

動物たちはぼくの先生
日高敏隆(青土社 2013年)
2014/04/07更新201403号
エッセイのような形式なので、気軽に読み始めてほしい。
だが初っ端の<打ち込んではいけない>からもうシビレる。「高校を卒業する君たちへ、などと今さらあらたまって何をいったらよいのだろうか?」で始まる本文は、初出掲載誌が『高校教育展望』。なるほど。これを書いた当時、50代半ばの日高先生は「ぼくらの高校はいわゆる旧制高校だから…」と昔話をするのだが、これがなかなかのハードボイルド。家計を助けるアルバイトからしてドイツ語やフランス語、果ては複式簿記まで勉強しておられて、しかしかわいい女子も意識していて、なんというか、さすがである。だが肝要なのはここから。
先生はこの状況を「もっと勉強に専念できたら」と思ったそうだ。しかし、あとになってみると「もし勉強ひとすじにできていたら、そしてあとは遊ぶことだけに時間を使えるという生きかたを、高校やその後にすることができていたら、今ごろはどんなに寂しい人間になっていたことか」と思い返し、こう断言するのだ。
「絶対に一つのことに熱中してはいけない」
いやぁ、もはや痛快。今どき「打込むことを見つけなさい」と言われることはあっても、逆はないだろう。ましてや「一人の女や一人の男に熱中して、その人と結婚してしまったりしては絶対にいけない」と来た。ここにはちゃんと先生個人の考えが書かれている。そして前後に、それを裏付ける文章がすらりとある。そういう本である。
幾つかの章立てに分けられてはいるが、初出一覧を見ると掲載誌はさまざまである。内容も、先生が昆虫学者を志した少年時代から、つい最近の出来事まで、動物行動学にひっかけた話題もあれば、日常エッセイのようなものもありという感じで、一見とりとめもない。が、読み終わると何とも言えぬ、先生の声が脳内に残る。そんなだから、冒頭に書いたとおりまずは気軽にとりかかり「へぇぇ」「ほぉぉ」と思えばいいと思う。それで充分に充実した時間が過ごせる。うん、そういう本である。
そう、先生が、精一杯生ききっている感触が、一冊に満ちている。教室の研修員が「能の研究をしたい」と言い出したときの「ぼくも前から興味がある」と渡りに舟と取り掛かる先生。能って、伝統芸能の能ですよ。先生とその研修員の方は、何度も何度もビデオを見てアタマをひねり、立派に国際動物行動学会で発表するまでにした。「○○を研究してみたい」とつぶやいてこれほど共に考えてくれるなんて、そりゃあ先生の教室が豊かなハズである。または、どんな葉っぱも食べないタイの大型カタツムリが、なんとエノキタケにかぶりつくことを発見した留学生と共に一路東北タイに飛び、山でキノコからカタツムリを引っぺがしてみる先生。「ぼくはそのときの感銘を今も忘れられない」こういう人生は、どんな気持ちがするものだろう。いや、自分にだってそんな瞬間があるハズなのに、日常からこぼれてしまっているようなのだ。これではいけない、と、つい思う。そういう本である。
<石器時代としての大学>はぜひ一読を。大学の存在価値について書いた興味深い章である。学年もさまざま、院生や研究生、研修生までいて、先生も老若男女、事務職員も大勢いる。そんな大学というものを「石器時代にも似てる」と歓迎するさまは、とてもユニークだ。新入生の方には特におススメしたい。
そしてエピローグの「渋谷でチョウを追った少年の物語」は、まったくお涙頂戴ではないのにあやうく泣いてしまうところだった。動物行動学研究の草分けであるコンラート・ローレンツについて、懐かしく語りながら、彼の説がすでに過去のものになってしまった現在でも「研究とはそういうもの」と言い切る。「形を成すことをめざしているのではない。大事なのはプロセス」という言葉を、今は忘れないようにしたい。それが何か、自分の長年の疑問の回答になるような、そんな気がする。
つまり、そういう本である。伝わっただろうか。
図書館 司書 関口裕子