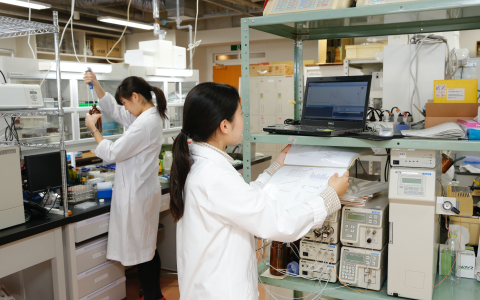「この一冊」 図書のご紹介


- 大学案内 About us
- 学部・大学院 Faculty Guide
-
入試情報
Exam Guide
- 大学機関 施設 University facilities
- 研究・産官学連携 Research and collaboration
- 学生生活 Student life
- 社会貢献・連携 Social Contribution and Cooperation
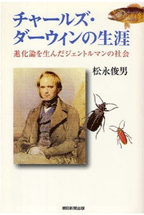
チャールズ・ダーウィンの生涯
進化論を生んだジェントルマンの社会
松永俊男( 朝日新聞出版 2009年 )
2014/11/27更新201410号
本を読んでいるあいだ、別世界にトリップできると、よく言うでしょ。
それを久々に味わいましたね。えぇ。SFやサイコホラーとはまた違った意味で、日常とかけ離れた世界でした。
働かないんだもん、みんな! 働かないのが当たり前の人ばかり出てくるのだ!
いや、確かにね、貴族とか王族とか、パンがなければお菓子を食べればいい方々はいますよ。でもそれはもう何万光年もかけ離れた上つ方々のことで、ダーウィンって科学者だし、近代人だし、もうちょっと現実的な存在だったわけですよ。
でも、違った。ダーウィンも、ダーウィンのお嫁さんも、みんなリッチ。そもそも嫁も母も、あのウェッジウッド一族のお嬢さんで、結婚のお祝いにダーウィン、両家から年金もらっちゃって、それだけでもう働く必要がなかった。貴族じゃないけど富裕層。働かないのがステイタス。弁護士や医者でも飾りみたいなもの。つまりダーウィンは、『高慢と偏見』に出てくるようなジェントルマンのひとりだったのだ。
本書を読むと、彼らの土壌というか、いわゆる上層社会の内幕がかなり面白い。名高いケンブリッジの学位も当時は、日本的に言えばゆるゆるである。しかし読むほどにわかるのだが、つまり「進化論」などというお金にならない研究を嬉々として続けられるのは、働かなくていいからなのだ。収入のためにではないが、まったくの余暇でもない「人生を豊かに生きるために生涯打ち込む研究」を持つ人々が、大英帝国を支えていたのである。
そんなダーウィンのビーグル号でのお役目は「艦長のお話し相手」だった。艦長は英国王の血をひく貴族。当時、英国海軍の艦長は、長い航海のあいだ乗員と個人的に接してはいけなかった。「耐えられん」と思った艦長は、ジェントルマンでケンブリッジ出身で、ナチュラリストとして体裁の整ったダーウィンを「個人的に」乗せたのである。もちろん無給。彼の旅費はぜんぶ、ダーウィンの父親が負担したそうだ。
なんというか、ちょっと現代とは違う感覚だ。ダーウィンは27歳で帰国。一生仕事せず、研究し続けた。39歳のとき父親が死去、受け継いだ遺産を順調に運用して(この方面でも有能だったのだ)73歳で亡くなり、ウェストミンスター寺院に葬られた。33歳からはケント州などカントリーサイドに住み、庭師や御者や料理人やメイドといった大勢の使用人、そして10人生まれた子どもたちに囲まれて過ごした。
以前読んだ『幕末日本探訪記』の著者が英国の「プラントハンター」で、中国や日本から植物を持ち帰り、ついでにインドにお茶の木を大量導入して茶産業を発展させたりした人だった。この紀行文がまたケッサクで、白人には物騒な幕末だってのに、大繁盛の植木市に驚嘆し、市井の花壇にうっとりし、次々とお目当ての木や花をゲットする。わざわざ極東まで来る甲斐があるのか疑問だったが、本書で納得。有名な王立植物園キュー・ガーデンは、大英帝国の各地から集めた植物や農作物を品種改良して発展させたが、ここが王立となったのは本書の頃だったのだ(園長も登場する)。
それは確かに大英帝国に貢献する事業だった。が、どこか純粋に知的好奇心というか、探究心に突き動かされてのものが感じられる。プラントハンターの彼だって、意欲を持った研究者でもあった。英国には、彼らを抱えるだけの力があったのだ。
かつて、こういう人々が牽引役だったのは、英国のみではない。が、ジェントルマンというどこか浮世離れした存在が、とてもそれに似合わしいのである。本書は、これまでの定説を丁寧に検証した優れた伝記であり、『種の起源』をめぐる騒動も読み応えがあったが、読後の印象は、やはり「ジェントルマンたちのお話」であった。
時は、ちょうど幕末。ダーウィンが種の研究をしていたのは、日本が黒船来航からの混沌にあった時期である。世界は大きく動いていた。カントリージェントルマン型研究者も、彼の世代が最後だったようである。彼の子供たちは著名な研究者や銀行家や実業家となったが、カントリーには住まず、ケンブリッジで暮らした。
図書館 司書 関口裕子