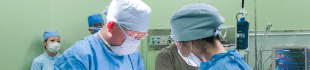教員からのレポート Report


- 大学案内 About us
- 学部・大学院 Faculty Guide
-
入試情報
Exam Guide
- 大学機関 施設 University facilities
- 研究・産官学連携 Research and collaboration
- 学生生活 Student life
- 社会貢献・連携 Social Contribution and Cooperation
アメリカからペットを連れて帰るには?
准教授 小柳 円(動物生体防御学教室)
かれこれ17年前、私はアメリカのテネシー州メンフィスにある研究所でポスドクとして働いていました。友人が猫を飼っていた影響で、猫を飼おうと決め、週末になると保護犬猫施設を何軒か尋ねてみたものでした。運命の出会い?はThe Humane Society of Memphis and Shelby County(https://memphishumane.org)という、アニマルシェルターを訪れた時でした。20匹ぐらいは猫さんたちがいたでしょうか?施設の人に、「気に入った子がいたら個室で遊べますよ」と言われ、1匹の猫さんを指し、「この子は?」と聞いたら、「もう、譲渡先が決まってる」と言われ、「じゃあ、この子?」、「その子も決まってる」、「じゃあ、この子!」「OK!」ということで、これが私と“さちおくん”との初めての出会いとなったのでした。最初の印象は他の猫さんに毛繕いをしてもらって自分はしない、というお姫様?(メスかと思っていたので)のような子でした。元々はTimid(臆病な)という名前がついていたこの子は宅配の人にも火災探知器の検査の人にもすり寄るような非常にフレンドリーな子に育ちました。当時のこの施設では譲渡するにあたり、住んでいるアパートで猫が飼えるかどうかを確認され、アパートに支払った前金300ドルの証明書程度であっさり譲渡成立しました。費用は他には去勢手術、ワクチンとマイクロチップ程度でした。それから夢のような睡眠不足の日々が15年続くこととなりました。

その1年後、再びシェルターを訪ねたところ、生後半年ぐらいの可愛らしい三毛猫ちゃん、のちに麗子ちゃん(元々はAudrey)と出会うことになります。非常にシャイで譲渡後、数日間はソファーの下に隠れてしまい、出てこなかったのを覚えています。最初は悪かった毛並みがだんだん綺麗になっていきました。
さて、私は一生アメリカに住むつもりはありませんでしたので、いつか日本での就職を見つけ帰らねばなりません。ビザもそろそろ切れそうだということで、すぐに猫さんを日本に運ぶための準備を進めました。日本は当時も現在も狂犬病の発生がないため、アメリカから日本にペットを持ち込むためにはいくつかのステップを踏む必要がありました。
(https://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/import-other.html)
1. マイクロチップによる個体識別
2. 不活化ワクチンによる複数回の狂犬病予防注射
3. 農林水産大臣が指定する検査機関での狂犬病ウイルスに対する血清中和抗体価の確認
4. 180日間の輸出(帰国)待機
5. 輸入予定日の40日前までに輸入に関する事前届出
6. 必要事項が記載された輸出国政府機関発行の証明書の取得
2のワクチンについて、当時はアメリカでは組換え体を利用した狂犬病のワクチンが主流でしたが、不活化ワクチンを注射する必要があったため、獣医さんに説明し、不活化ワクチンを用意してもらう必要がありました。3についても獣医さんに検査機関を伝え、そちらに血液を送ってもらい書類を作成してもらう必要がありました。5についてはメールにより提出しました。大変だったのが6の証明書の取得でした。メンフィスは州都ではなく、この手続きができるのは車で3時間のナッシュビルというところまで行かなければなりませんでした。しかも、書類の不備があり、帰国ギリギリにもう一度書類を取りに行くことになり苦労したことを覚えています。そして帰国当日、だだっ広い空港のチェックインカウンターにて、ケージから猫さんを一旦出して、と言われた時には、今逃げたらどうしてくれるのかとヒヤヒヤしたのを覚えています。メンフィスから成田には直行便がなく、ロサンゼルスの空港で乗り継ぎをしましたが、ちゃんと猫さんが乗ったことを報告してもらえたので安心して帰国することができました。しっかり準備ができていたので、日本での入国はすんなりと通過することができ日本での生活がスタートしました(次回に続く??)。