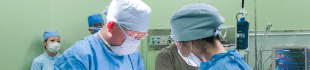教員からのレポート Report


- 大学案内 About us
- 学部・大学院 Faculty Guide
-
入試情報
Exam Guide
- 大学機関 施設 University facilities
- 研究・産官学連携 Research and collaboration
- 学生生活 Student life
- 社会貢献・連携 Social Contribution and Cooperation
動物の“健康”について考える
准教授 戸澤 あきつ(動物行動福祉学教室)
この4月に着任しました、動物行動福祉学教室の戸澤です。着任して3ヶ月が経とうとしていますが、新規環境(と私の専門分野では表現します)は慣れないこと・わからないことが多く、まだとまどうこともあります。ただ、それも“良い刺激”となる部分があり、知的好奇心が掻き立てられています。
「はじめまして」ですので私の研究分野について少し紹介したいと思います。
皆さんは「動物の健康」と聞くとどのようなイメージを持たれますか?
多くの方が「病気にならないようにする」というイメージを浮かべると思います。しかし、私たち人間も含めて、程度の差はありますが自分で物事を考えたり、「嫌だ」「好きだ」といった感情を持つ動物にとっては「病気にならない」という肉体的な健康だけでなく、こころの状態、つまり精神的な健康についても考える必要があります。精神的な健康状態は肉体的な健康状態とも関係する部分があります。たとえば、「嫌なことがあった」という精神的な健康状態が思わしくないときに食欲がなくなることがあります。そのような状態が続き、食べられない=栄養が適切に摂取できない状態が続くと肉体的にも不健康な状態になってしまいます。
このように、“健康”は必ずしも肉体的な側面だけを見ていれば良いわけではなく、精神的な側面からのアプローチも必要です。この考え方が「動物福祉(アニマルウェルフェア)」につながります。
では、私たちはどのように彼らの精神状態を知り、精神的な健康状態について考えていけばよいのでしょうか。人間同士とは異なり、異種の動物とは言語コミュニケーションをとるのが難しく、直接的に話を聞けません。動物を理解する方法のひとつに「行動」が挙げられます。動物はイライラしたり、不満がたまっていると攻撃行動が多くみられるようになります。また、心理的な状態が安定していると仲間のことを気にかけることができ、親和行動(仲間と仲良くする行動)が多くなることがあります。このように、精神状態を反映している行動を指標として、そのような行動がどの程度見られるかを観察し、動物たちのいまの状態を理解しようとします。
動物の健康状態はもちろん行動のみで測れるものではありません。生理状態や内臓機能、近年では腸内環境も関係するといわれていたり、様々な側面から動物を理解する必要があります。科学的な分野からアプローチして動物たちを可能な限り理解し、良好な健康状態の維持やよりよい生活の提供にはどうしたらいいか?を考え、日々研究を行っています。

▲写真1
外にいるウシは気持ちよさそうだなと思いますが…
一方で、暑そうだな、虫にたかられてイヤだろうな、と思うときもあります。
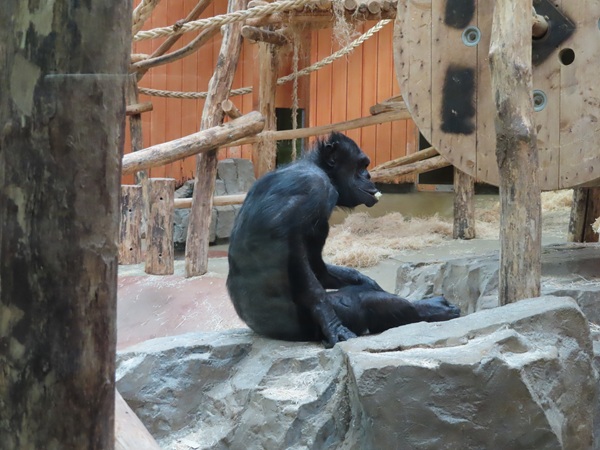
▲写真2
動物園でも「彼らはなにを考えているんだろう…」と観察してしまいます。