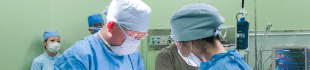教員からのレポート Report


- 大学案内 About us
- 学部・大学院 Faculty Guide
-
入試情報
Exam Guide
- 大学機関 施設 University facilities
- 研究・産官学連携 Research and collaboration
- 学生生活 Student life
- 社会貢献・連携 Social Contribution and Cooperation
田んぼと動物
准教授 桑原 考史(食料自然共生経済学教室)animal-report-teachers-072/

▲宮城県での子実用(飼料向け)とうもろこし生産現場の様子
今年の夏は、お米の売り切れや値上がりが発生しました。
皆さんのご家庭でも、食卓の話題になったり、お米以外の主食(パン、麺)を食べる回数が増えたりしたのではないでしょうか。
お米はどこで作られているでしょうか――というのはあまりにも簡単なクイズですね。答えは田んぼです。田んぼは日本の耕地の半分以上を占め、私たちの食を支える重要な基盤です。
同時に、田んぼは、動物の生存や飼養にかかわる場でもあります。
一つに、田んぼは生態系の構成要素であり、水生生物の生息地や鳥類の採餌環境となっています。コウノトリやトキといった希少鳥類をシンボルとしたお米づくりが行われている地域もあります。田んぼのこうした側面は、洪水防止や景観形成等と合わせて「多面的機能」と呼ばれています。
少し補足すると、田んぼは外部環境に開かれているがゆえに「多面的機能」を持つのですが、その半面シカやイノシシ、スズメなどから農作物被害(鳥獣害)を受けることもあります。鳥獣害は現在の農村が直面する深刻な問題の一つで、最近は都市部にまで影響が広がりつつあるようです。
田んぼと動物の関係の話に戻りましょう。二つに、田んぼではごはん用のお米だけでなく、家畜のエサ(飼料)も作られています。田んぼで作られる代表的な飼料として、お米の実の部分を飼料向けに作る飼料用米、稲の茎や葉を含めて利用する飼料稲があります。
さらに最近注目されているのが、子実用とうもころしの生産です。
とうもろこしといっても、皆さんがゆでたり焼いたりして、あるいは缶詰で食べるスイートコーンとは少々異なり、デントコーンという種類のとうもろこしです。

▲子実用とうもろこし
国内では以前から、デントコーンの実の部分(子実)と茎葉を丸ごと収穫したものが飼料に用いられてきました。これは青刈りとうもろこしと呼ばれます。
それに対し、子実だけを用いる飼料向けとうもろこしの国内生産面積はごくわずかで、ほぼ100%を海外から輸入しています。とうもろこしの年間輸入量は、国内で年間に消費されるごはん用のお米の2倍以上(1,500万トン)もあり、その8割近くが飼料として用いられています(農林水産省「令和4年度食料需給表」)。
では、なぜ子実用とうもろこしの国内生産が注目されているのでしょうか。要因の一つは、ウクライナ危機や円安による輸入飼料価格の高騰です。しかしそれだけではありません。もともとはお米を作る場所である田んぼを、私たちの食生活に合わせてどう使っていくか、という問題もかかわってきます。
国内のごはん用のお米の消費量は毎年10万トンほど減少しています(ちなみに2023年秋~2024年夏は逆に前年比11万トン増となり、これが値上がりや売り切れの一要因になりました)。一方、お肉、チーズなどの畜産物の消費量は数十年前に比べて大きく増加しました。しかし国内の農地利用は、こうした食生活の変化を反映したものに必ずしもなっていません。お米(稲)だけでなく、水田で麦や大豆、飼料向けの子実用とうもろこしを作ることは、こうした状況(「食生活と農村景観のギャップ」と表現されます)を変えるための試みなのです。
今夏、学生の卒業研究の一環として、宮城県大崎市の古川農協管内で行われている子実用とうもろこしの収穫実演会に参加してきました。同地では3年間の栽培実証事業が行われており、今年が3年目にあたります。害虫被害や獣害、雑草などの課題を1つずつ乗り越え、今年は品質、収量ともに豊作が見込めるのではないかとのことでした。収穫した子実用とうもろこしは、県内の肉牛に給与されているそうです。
このような取組みがさらに普及するためには、どんな課題を克服しなくてはならないでしょうか。当研究室では今後この点について調査研究を行う予定です。
今回は田んぼと動物の関係の一端を紹介しました。今年の新米を食べるとき、少しでも思い出してもらえれば幸いです。興味がわいた方はぜひオープンキャンパスにお越しください。