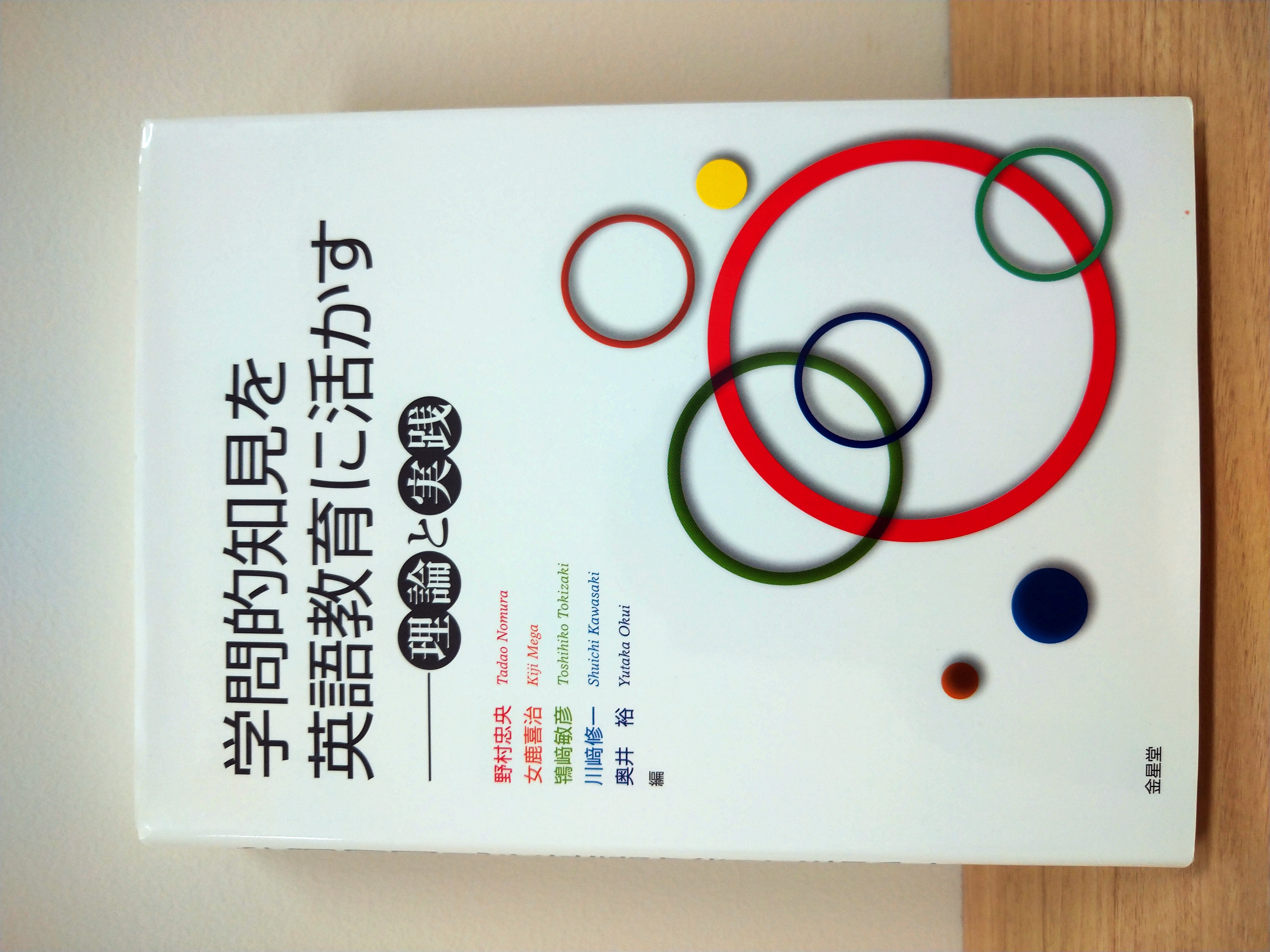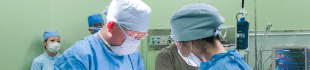教員からのレポート Report


- 大学案内 About us
- 学部・大学院 Faculty Guide
-
入試情報
Exam Guide
- 大学機関 施設 University facilities
- 研究・産官学連携 Research and collaboration
- 学生生活 Student life
- 社会貢献・連携 Social Contribution and Cooperation
疑問を持つことの大切さ
教授 鴇﨑 敏彦(教育実践学教室)
私が教員になることを決意したのは小学校4年生の時のある出来事がきっかけだったのですが、当時は教えることを生涯の職業にしたいという強い思いのみを抱いていたので、その後しばらくは何の教科の教員を目指そうか迷っていました。
そんな私が英語の教員になることを決意したのは中学校1年生の時、当時通っていた学習塾でいわゆる頻度の副詞を教わったことがきっかけでした。それまで、英文中の副詞の位置は「動詞を修飾する場合は動詞の後ろで、目的語がある時はその目的語の後ろ、形容詞・副詞を修飾する場合はその形容詞・副詞の前に置く」と教わってきましたが、頻度の副詞を教わった際には、「always, usually, often, sometimes, seldom, neverなどを頻度の副詞と呼び、原則として一般動詞の前、be動詞・助動詞の後ろに置きます」という説明を受けました。
その時、もちろん例外的な規則として暗記するだけでもよかったのですが、「同じ副詞なのに、なぜ頻度の副詞だけ英文中での位置が変わるのだろう」という疑問が浮かんだのです。そして、「頻度の副詞は他の動詞を修飾する副詞と何が違うのだろう」ということを考えているうちに、「頻度の副詞は100%の肯定文から0%の否定文までを段階別に表現している語である。だから、否定文を作る時に使うnotと同じように動詞の近くに置くのではないか。そういえば、notも英文中では一般動詞の前、be動詞・助動詞の後ろに置かれているではないか」ということに気がつきました(下記の例1、例2参照)。更に、その後の学習で、not自体の品詞が副詞であることを知った時の感激は、今でも鮮明に覚えています。
- 例1:He is not happy. 「彼は幸せではありません」
- 例1:He is always happy. 「彼は常に幸せです」
- 例2:I do not wear jeans. 「私はジーンズをはきません」
- 例2:I always wear jeans. 「私は常にジーンズをはきます」
このことがきっかけで、「言葉というのは人間が作り上げてきたものなのだから、言葉の規則には何か必ず理由があるはずだ」と考えるようになり、常に「なぜそうなるのか」という疑問を抱きながら英語学習を続け、英語という言語の奥深さに魅了されていきました。その頃より、「とにかくそのまま覚えなさい」と言うのではなく、英語学習者が言葉の成り立ちをきちんと理解した上で英語が使えるように指導できる教員になりたいと思うようになったのです。
その目標を達成するために、私は学部と大学院で英語学(英語史)を専攻し、中学校、高等学校、専門学校、大学と様々な教育機関の英語の授業の中で、自らの専門性を活かして、受講者の知的好奇心を喚起するような授業展開を研究テーマの一つに掲げて、実践してきました。そして、その実践を通じて、英語に関するどの研究分野にも英語教育に活かすことができる学問的知見があるのではないかと考えるようになりました。そこで、ある学会で、自ら発起人となって「学問的知見を英語教育に活かす」というシンポジウムを企画し、編著者の一人として、写真にある『学問的知見を英語教育に活かす―理論と実践』(金星堂、2019)という書籍を刊行するに至ったのです。
中学校1年生の時に抱いたちょっとした疑問が、まさかここまでの活動に発展することになるとは、当時は夢にも思いませんでした。人生、何がきっかけでどのように物事が発展していくか、本当に分からないものです。これからも、様々なことに疑問を持ち、そして、その疑問を解決する努力をすることで、自分自身の活動の幅を更に広げていきたいと思っています。