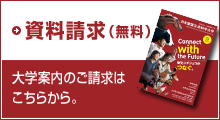日本獣医生命科学大学 FD委員会主催講演会
平成24年度第2回FD講演会「単位制度におけるシラバスの役割」を開催
 平成24年度の第2回FD講演会が、去る10月18日(木)の午後4時より6時まで、本学B棟412室で開催された。後期授業が始まり、多忙な時期にも関わらず、池本学長先生を始め教職員約50名が参加した。今回は、立命館大学教育開発推進機構教授の安岡高志先生に「単位制度におけるシラバスの役割」という演題で講演をしていただいた。安岡先生は、1980年代にわが国で初めて実施された大学での「学生による授業評価アンケート」を企画された著名な先生である。文部科学省の様々な評価委員も努められており、「授業が変われば大学が変わる(プレジデント社)」の著者のお一人である。今回の講演では、「シラバスに書かなければならないこと」並びに「シラバスに記載すべき学生の到達目標の書き方」等に関する内容をお話しいただいた。
平成24年度の第2回FD講演会が、去る10月18日(木)の午後4時より6時まで、本学B棟412室で開催された。後期授業が始まり、多忙な時期にも関わらず、池本学長先生を始め教職員約50名が参加した。今回は、立命館大学教育開発推進機構教授の安岡高志先生に「単位制度におけるシラバスの役割」という演題で講演をしていただいた。安岡先生は、1980年代にわが国で初めて実施された大学での「学生による授業評価アンケート」を企画された著名な先生である。文部科学省の様々な評価委員も努められており、「授業が変われば大学が変わる(プレジデント社)」の著者のお一人である。今回の講演では、「シラバスに書かなければならないこと」並びに「シラバスに記載すべき学生の到達目標の書き方」等に関する内容をお話しいただいた。
まず、最近、日本の大学生の勉強時間が、米国大学生と比べて極めて少ない現状を紹介され、それが単位制度の理解の不十分から生じていることを説明された。大学設置基準にある単位制度では、通常の授業1単位の場合、「授業は45時間の学修を必要とする内容をもって構成すること」と規定されていることを取り上げられ、その内訳が、教室での学修時間が15時間、教室外での30時間であることを示された。シラバスは、学生に教室外で30時間の学修をさせるための小道具であると解説され、シラバスの本来の役割を納得することができた。
次に、学生が教室外で勉強するようなシラバスを書くためには、まず、授業の組み立てを変える必要があると説明された。具体的には、小テスト、レポート、グループディスカッションなどを授業に取り入れて、学生に絶えず学習させることが重要である。また、これらの学修成果をどのように成績に反映させるかを、シラバスに記載しておくことが大切であると述べられた。その際に、これらの学修成果は、成績全体の3分の2くらいまで反映させることが大切であり、それにより教室外での学修時間を増やすことができると説明された。
さらに、シラバスには、「学生が理解・想像できる明確な到達目標」を記載することが大切であると述べられた。各授業科目の到達目標は、大学が設定しているディプロマポリシーに基づいて観点別に設定されたもので、すべての授業科目の到達目標を身につければ、ディプロマポリシーに記載された学生を養成できることになると解説された。最後に、到達目標の書き方に関して、具体的な例を挙げながらわかりやすく説明してくださった。
以上の講演から、良いシラバスを書くためには、学生の学修時間を増やすように、まず授業そのものを変えることが大切であるとまとめられた。講演後には、教員による質問もあり、2時間の有意義な時間を過ごすことができた。参加してくださった教員によるアンケート結果でも、ほとんどすべての先生が、「満足した」、「今後の教育活動に役に立つ」と回答された。
これからも、FDに関わる様々なテーマを取り上げ、講演会を企画してゆきますので、ご参加をよろしくお願いいたします。また、FD活動へのご協力もよろしくお願いいたします。
(FD委員会委員長 西村敏英)