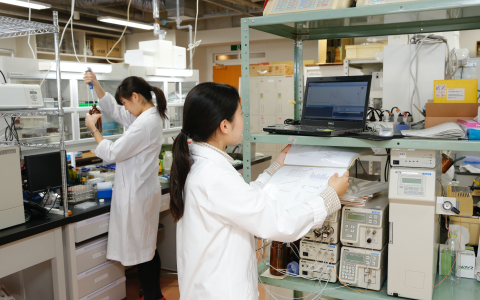牧場だより「継・いのち」


- 大学案内 About us
- 学部・大学院 Faculty Guide
-
入試情報
Exam Guide
- 大学機関 施設 University facilities
- 研究・産官学連携 Research and collaboration
- 学生生活 Student life
- 社会貢献・連携 Social Contribution and Cooperation
第37号:アニマルファームの丑年の1年
吉村 格(准教授/牧場長補佐)
2009/2/3 更新

職員は予想に反し娩出された仔牛の股間に丸いものを見つけると、未だ卑猥でもないそれそのものには全く罪はないのであるが「なんだ-オスかよ-」と言わなければ気が済まない習癖をもっている。実習中に分娩が始まると学生達は超真剣モードで母子の様子を見守ってくれるが、ついつい我々が言わなくてもいいことを口走ったりすると、その後に提出されたレポートには必ず「附属牧場で働く職員に愛はない。男女を差別する人間だ」みたいな強烈な言葉で埋め尽くされる。
確かに、酪農は産ませて乳を搾り経営を存続させていくわけであるから、妊娠させるための授精技術においては苦労の連続であるが、産まれた仔に「ついてる」か「ついてない」かは努力と人知の及ぶところではないのであるから所詮それは「たまたま」なのである。自然が決めたことに異を唱えることは、それと不即不離にある農業者にとって天に唾する所業である。今後は学生に気づかれない程度のため息に止め、オスであったとしても気持ちよく受け入れることにしよう。ほぼ2回に1回はついてしまうことになる娩出後のため息は、帰属集団である酪農家と同じ思いであるが、かつて働いていた競走馬の繁殖牧場では「なんだ-メスかよ-」と嘆いていたのが懐かしい思い出である。
さて、牛からの新年早々のプレゼントは2頭続けての体躯の美しいブラウンスイスの雌であった。果たして富士アニマルファームの丑年の1年は「ついている」のか「ついていない」のか? 「運」であればついてくれることを天に祈りたい。