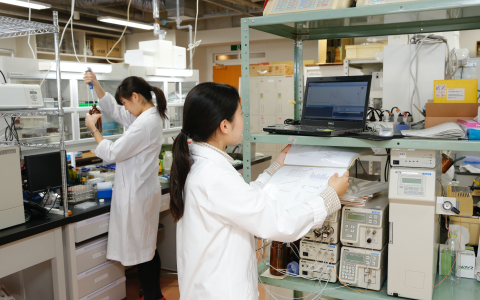「この一冊」 図書のご紹介


- 大学案内 About us
- 学部・大学院 Faculty Guide
-
入試情報
Exam Guide
- 大学機関 施設 University facilities
- 研究・産官学連携 Research and collaboration
- 学生生活 Student life
- 社会貢献・連携 Social Contribution and Cooperation
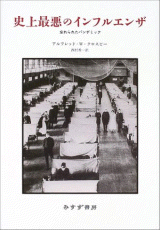
分類番号は493.87(書架番号13。入り口から見て左側)。ノンストップで読める迫力のノンフィクションで、内容的に古いかなーと思ったのは甘かった。岩波新書に『感染症とたたかう』(岩波870)、『新型インフルエンザ-世界がふるえる日』(岩波1035)があるので、そちらも読んでみようと思う。
史上最悪のインフルエンザ -忘れられたパンデミック-
アルフレッド・W・クロスビー 著 西村秀一 訳(みすず書房 2004年)2009/9/1更新 200916号
2003年の総選挙から「マニフェスト」なる言葉が急激に普及した。では2009年の今年は?今年は世界的流行語がある。「パンデミック(感染症の世界的流行)」だ。
そしてパンデミックの典型としてよく紹介されるのが、1918年の「スペイン風邪」である。
まだ肺炎の致死率が高かった当時、この“スパニッシュ・インフルエンザ”は「肺ペスト」かと医者を恐怖に陥れるほど劇症の肺炎を併発し、世界中から生命を刈りとって行った。25歳から35歳ほどの体力旺盛な若者たちを、ウィルスは殊のほか好んだ。
そこまでは知っていた。
が、私はそれが第一次大戦真っ只中、という事を本書でようやく実感したのである。ヨーロッパ戦線に向けて、若いアメリカ兵が毎月二十五万人かそれ以上送られていたのだ。彼らは咳とくしゃみを飛ばしながら全米から集められ、狭いキャンプで訓練を受け、戦艦に鮨詰めになって海を渡る。国境も人種も関係なく、地球上の人間を舐めつくすようにウィルスはアメリカまで戻ってしまう。おそらく変異もしただろう。戦時公債購買キャンペーンで盛り上がり、ウィルソン大統領に熱狂する市民の中を、嵐のようにウィルスが駆け巡るさまは壮絶と言うほかない。
新型インフルエンザは恐ろしい。劇症型に変異してしまったらと考えると更に怖い。それは世界中が知っている。できる限り闘わなければ。そう思っている。
が、だからと言って時計は止まらないのだ。パリ講和会議の駆け引きの中、トップ政治家たちがインフルエンザに翻弄される有様は悪夢のようである。ひとごとではない。例えば本命校の入試、社運をかけた合併会議、歴史的コンサートの舞台本番、自分の結婚式、誰にもまかせられないあらゆる重大事を前にしていたとしても、インフルエンザは分け隔てなく襲ってくるのだ。
戦争は始まっていた。百万人単位の人間が短期間で移動しまくるのを止められる人間はどこにもいなかった。現在、治療法は見違えるほど発達しているはずだ。だがこの春、すでに社会は混乱を幾つも目にしている。そのもっとも劇的な実例は本書にある。消防士が、警官が、電話交換手が、交通機関の働き手が、医師が、看護婦が、そして小さな子供を抱えた親たちが倒れていく。墓堀り人夫が休みなしに働いても死体は川のように溢れてしまい、棺おけ屋が寝ないで棺を作り続けても追いつかなかった。
行政がもっとちゃんと対応するべきだった。そうかもしれない。が、本書を読むと「行政がすべてコントロールして当然」とはとても思えない。彼らは所詮、人の子であって、神ではないのである。
地震や戦争と違い、人の体のみを蝕み、怒涛のように通り過ぎていったパンデミックは記憶に残りにくい。が、本書にはその欠片が集められ、静かに収められた。地獄のようなあの時、世界を支えたのは医師や看護士、休校になった学校の教師、引退した警官や運転手、聖職者、つまりは名も無い市民たちだった。肺を血と液体でいっぱいにして死んでいくさまを見ながらも、大勢のボランティア達が命がけで闘ったのである。
ウィルスのみが生命を謳歌する戦艦の中、高熱と空腹と水浸しの嵐の甲板を耐え、ようやくベッドにありつけた兵士。彼は、真夜中にひとりの看護婦が、十二日間履き続けた靴下を脱がせて足を洗ってくれたのを、半世紀たってからも「人のかたちをした奇跡」として忘れなかったという。
神ならざる身は、今できることをするしかない。できるかぎりに。
図書館 司書 関口裕子