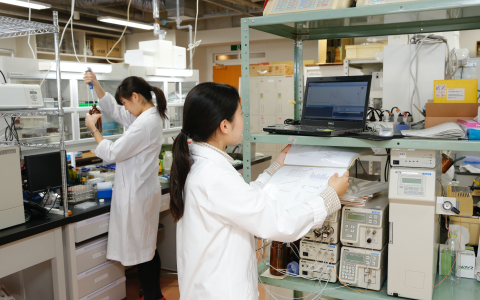「この一冊」 図書のご紹介


- 大学案内 About us
- 学部・大学院 Faculty Guide
-
入試情報
Exam Guide
- 大学機関 施設 University facilities
- 研究・産官学連携 Research and collaboration
- 学生生活 Student life
- 社会貢献・連携 Social Contribution and Cooperation

漱石の倫敦、ハワードのロンドン:田園都市への誘い
東秀紀 ( 中公新書 1037 1991年)
2017/04/03更新201703号
昨年は夏目漱石没後100年、今年は生誕150年、なんとキリのいいことよ。当館でも勿論、漱石を読める(文庫もありますよ)が、今回はひとつ珍しい一冊をご紹介したい。
本書の著者は建築学がご専門だが、小説家でもある。なるほど、小説も面白そうだ。なにせ、本書がめっぽう面白かった。
あとがきによれば漱石と同様、著者の東氏もロンドンに留学経験があり、英国における近代都市計画の誕生について書いてみたい、とかねて思っておられたそうだ。しかし英国で学んだことは、建築の物的な側面だけでなく、経済や社会政策まで含めた総合的な学問であり、それらを含めてどう書いていいものか、考えあぐねていたという。その彼が辿りついたのが、漱石のロンドン留学をからめた視点からの執筆だった。
夏目漱石が訪れた頃、ロンドンはどんな街であったのか。本書には無いが、わかりやすいのはシャーロック・ホームズだろう。漱石滞在時に起きた(もちろん架空の)ホームズの事件には例えば『バスカヴィル家の犬』がある。また、バーナード・ショーの『ピグマリオン』が原作の『マイ・フェア・レディ』も、漱石訪英の少しあとが舞台である。さらに本書でも言及される「切り裂きジャック事件」が起こったのもそう遠い過去ではなく、10年ほど前であった(だから漫画の『黒執事』も同時期か)。
これらをドラマなり小説なりでご存知の方には、漱石が見たロンドンの光景をご想像しやすいのではないだろうか。物質的な繁栄と、その代償が形になった大都市は、濃い霧に覆われた場所であった。『ホームズ』でも一歩踏み込めばスラムという市街が何度も登場する。漱石は別に望んだわけでもないのにここで国費留学生として、たったひとりで過ごすことになったのである(偶然にも、彼が師事したシェイクスピア研究者のクレイグ氏はベイカー街居住で、漱石は1890年に開通した地下鉄で通っていた)。
この漱石と、もうひとり本書の軸となるのがエベネザー・ハワードという人物で、彼とその周辺を語りながら「田園都市」計画について説明されるが、日本ではあまり馴染みがない概念である。なのでこのあたりは著者の面目躍如といったところか。ご想像のとおり世紀末のロンドンは居住環境としては問題が多く、当時でもジェントルマンと呼ばれる階層は、家庭は田舎に持っていた(ホームズ『もう一つの顔』などそうですね)。たとえ豊かでも人間的な生活と言えない、と反発する風潮はすでにあり、それらが田園都市構想を後押ししていたといえる。そういえば、ナショナル・トラスト運動を支援したビアトリクス・ポターも同時期の人物であり、最初の『ピーター・ラビットのおはなし』が出版されたのは漱石の帰国直前である。
明治期の日本が目指した近代的国家が直面していた問題を、漱石はその場で直に感じながら過ごしたのだ。彼のスコットランド滞在についての項は、読むと風が吹くように感じる。それほど本書はヴィクトリア朝末期ロンドンの時代性をうまく切り取り、読者をそこに封じ込めてみせた。
本書は都市論を論じた本といえるが、建築学に素養のあった漱石についての考察としても新鮮だ。反産業主義と言われたウィリアム・モリスやロセッティの思想、彼らとモリスの妻の三角関係から、漱石の『それから』以降の作品をみるくだりなど、読み応えたっぷりである。また、中産階級のやや下層にいたハワードと、ノーベル文学賞を受賞したバーナード・ショーとの友情にはすぐれて文学的な風味があり、ハワードにナイトの称号が与えられた際にショーが「それでは足りない」と言い切る場面など、あやうく泣かされるところだった。ショーの複雑で陰影に富んだ資質は、小説の素材にこそ相応しい。
30代半ばを異郷で孤独に過ごした日々が、文豪に及ぼした影響が大きくないわけはない。ヴィクトリア朝ロンドンを今後観たり読んだりする際も、本書は大いに影響しそうである。ロンドン、ロンドン、やはりロンドンについて読むのは面白い。そして、漱石について読むのも。
図書館 司書 関口裕子