食のいま


- 大学案内 About us
- 学部・大学院 Faculty Guide
-
入試情報
Exam Guide
- 大学機関 施設 University facilities
- 研究・産官学連携 Research and collaboration
- 学生生活 Student life
- 社会貢献・連携 Social Contribution and Cooperation
第20号:マヨネーズの値上げから思うこと 4/4
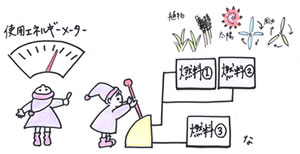
例えば、状況や用途に応じて複数の動力源を使い分け、化石燃料への依存度を低減させるハイブリッド車の技術…これを一般住宅や公共施設に応用して、化石燃料エネルギーと太陽光や風、地熱といったクリーンエネルギーの併用を普及することが考えられています。また、ある研究グループは、農産廃棄物や木質・草本系廃棄物などの未利用資源をバイオ燃料に変換して、海外の資源に依存しない循環型エコ社会を実現できないか調べています。食料と燃料の競合が起きない仕組みを備え、且つ採算がとれる(経済活動が成立する)システムの構築までは課題が多いようですが、農業や地域の整備と活性化にもつながるので成果が楽しみです。
ただし、大がかりな新しい仕掛けに頼り、食料価格の高騰に困ってばかりいるのは考えもの…。未利用の資源を導入した時の効果を引き出すには、個人が食料とエネルギーの両資源について消費を見直し、無駄を減らすことも求められます。





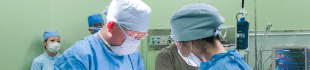








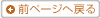

 「奈良井(金山)朝子先生のバックナンバーはこち ら」
「奈良井(金山)朝子先生のバックナンバーはこち ら」