食のいま


- 大学案内 About us
- 学部・大学院 Faculty Guide
-
入試情報
Exam Guide
- 大学機関 施設 University facilities
- 研究・産官学連携 Research and collaboration
- 学生生活 Student life
- 社会貢献・連携 Social Contribution and Cooperation
第48号:伝統の器を楽しむ食卓風景 -11月-
11月は黄色い柚子(ゆず)の収穫時期です。石川県の輪島では柚子を使ったお菓子‘柚餅子’(ゆべし、写真)作りがはじまります。


柚子の皮をきれいに残して果肉を取り出し、果肉ペーストと米粉あるいは餅粉、白味噌、砂糖などを調合して練り上げたものを柚子の中に詰めもどします。これを4~6ヶ月間、何度も蒸して自然乾燥させると‘柚餅子’の出来上がり。口当たりの粘稠性が甘味とあいまって非常に濃厚に感じられ、心地よいわずかな苦味が口に広がります。
もぎたての柚子の水分含量は果皮と果汁がそれぞれ75%および91%なのに対し、柚餅子の水分含量は30%(食品工学教室測定)にも低下します。食品の保存性を表す指標に水分活性(water activity)というものがあります。水分活性値が低いほど微生物の増殖が抑えられ、一般細菌はこの値が0.91以上、酵母は0.88以上、カビは0.80以上で増殖します。輪島土産の‘柚餅子’を研究室で測定したところ、水分活性は0.77でした。この値から、‘柚餅子’が日持ちする保存食品であることが分かります。
ところで、‘柚餅子’と同郷の輪島塗の名前を聞いたことがある人は多いでしょう。日本各地に漆(うるし)を使った塗り物がありますが、輪島塗の知名度はダントツの1位です。なぜ、これほど有名なのでしょうか? 輪島塗の歴史は古く、9世紀後半~10世紀前半の遺跡からも出土しています。そして江戸時代には、輪島塗の製造と販売を取りまとめる人たち(彼らのことを塗師屋(ぬしや)とよびます。)が、自分たちの製造した漆器を背負って全国を旅しながら売り歩きました。塗師屋たちは、輪島塗を購入してくれたお客さんのところに何度も足を運こび、手入れ法を伝授したり、修理をしてきました。このため、輪島塗の評判は非常に高くなり、品質が良くて長持ちする品物であるということが広く認知されていったのです。こうした販売後のきめ細かいサービスのほかに、丈夫な輪島塗と言わしめる理由がもうひとつあります。それは、輪島塗の縁の構造です。「布着せ(ぬのきせ)」と称して、漆を滲み込ませた布で器の縁を覆うもので、他の漆器にはみられません。この布張り工法が、丈夫で長持ちの特性を生みだしているのです。布を「着せる」と、まるで人に見立てたような言いまわしをするあたり、職人たちの輪島塗への愛情を感じます。
骨董店の隅のダンボールで、縁の欠けた輪島塗を見つけました。欠けてしまった傷口部分を拡大してみましょう。表面の朱色の漆と白色の木地とのあいだに、灰色の布の切れ端が見えますね。これが「布着せ」の布の正体です。写真の輪島塗は、残念ながら何らかの事情で縁が欠けてしまったわけですが、輪島塗の丈夫さの秘密である「布着せ」を目で確認できる貴重な品として、私は大切に保管しています。
もぎたての柚子の水分含量は果皮と果汁がそれぞれ75%および91%なのに対し、柚餅子の水分含量は30%(食品工学教室測定)にも低下します。食品の保存性を表す指標に水分活性(water activity)というものがあります。水分活性値が低いほど微生物の増殖が抑えられ、一般細菌はこの値が0.91以上、酵母は0.88以上、カビは0.80以上で増殖します。輪島土産の‘柚餅子’を研究室で測定したところ、水分活性は0.77でした。この値から、‘柚餅子’が日持ちする保存食品であることが分かります。
ところで、‘柚餅子’と同郷の輪島塗の名前を聞いたことがある人は多いでしょう。日本各地に漆(うるし)を使った塗り物がありますが、輪島塗の知名度はダントツの1位です。なぜ、これほど有名なのでしょうか? 輪島塗の歴史は古く、9世紀後半~10世紀前半の遺跡からも出土しています。そして江戸時代には、輪島塗の製造と販売を取りまとめる人たち(彼らのことを塗師屋(ぬしや)とよびます。)が、自分たちの製造した漆器を背負って全国を旅しながら売り歩きました。塗師屋たちは、輪島塗を購入してくれたお客さんのところに何度も足を運こび、手入れ法を伝授したり、修理をしてきました。このため、輪島塗の評判は非常に高くなり、品質が良くて長持ちする品物であるということが広く認知されていったのです。こうした販売後のきめ細かいサービスのほかに、丈夫な輪島塗と言わしめる理由がもうひとつあります。それは、輪島塗の縁の構造です。「布着せ(ぬのきせ)」と称して、漆を滲み込ませた布で器の縁を覆うもので、他の漆器にはみられません。この布張り工法が、丈夫で長持ちの特性を生みだしているのです。布を「着せる」と、まるで人に見立てたような言いまわしをするあたり、職人たちの輪島塗への愛情を感じます。
骨董店の隅のダンボールで、縁の欠けた輪島塗を見つけました。欠けてしまった傷口部分を拡大してみましょう。表面の朱色の漆と白色の木地とのあいだに、灰色の布の切れ端が見えますね。これが「布着せ」の布の正体です。写真の輪島塗は、残念ながら何らかの事情で縁が欠けてしまったわけですが、輪島塗の丈夫さの秘密である「布着せ」を目で確認できる貴重な品として、私は大切に保管しています。

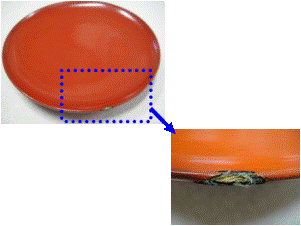





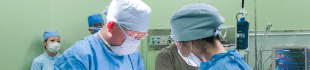








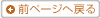

 「小竹佐知子先生のバックナンバーはこちら」
「小竹佐知子先生のバックナンバーはこちら」