食のいま


- 大学案内 About us
- 学部・大学院 Faculty Guide
-
入試情報
Exam Guide
- 大学機関 施設 University facilities
- 研究・産官学連携 Research and collaboration
- 学生生活 Student life
- 社会貢献・連携 Social Contribution and Cooperation
第82号:地理的表示(GI)と関東の産品
私たちの食には、日々の一皿にもその土地の風土や歴史が映し出されています。そうした「地域ならではの特性をもつ産品」を守り、消費者にとっての選ぶ道しるべとなるのが、地理的表示(GI:Geographical Indication)保護制度です。農林水産省が2015年に始めた制度で、2025年3月現在、全国で161品目が登録されています。

地理的表示(GI)保護制度
(農林水産省HP https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/より)
GI制度は、消費者にとっては「どこで、どんな食材なのか」が明確になる安心の目印であり、生産者にとってはブランド価値を高める大切な仕組みです。たとえば「夕張メロン(北海道)」「神戸ビーフ(兵庫)」「球磨焼酎(熊本)」など、全国的に名高いブランドが登録されています。
では、私たちの身近な関東圏には、どのような産品があるでしょうか。
関東圏のGI産品
- 東京しゃも(歯ごたえのある肉質で親しまれる地鶏)
- 新里ねぎ(軟白部が弓形に曲がる伝統野菜で、柔らかく甘みが強い)
鹿沼在来そば(小粒で香り豊か、タンパク質が低く雑味が少ない) - 高山きゅうり(一般的なきゅうりの3〜4倍の大きさで、青臭さ控えめ、シャキッとした歯ごたえとみずみずしさが特長)
- 江戸崎かぼちゃ(東京都と並ぶ指定地域)
行方かんしょ(ホクホク感と甘さで人気のさつまいも)
飯沼栗(栗として全国初GI登録。1つの毬に1果の大粒、甘く、伝統的な出荷選別が特徴)
水戸の柔甘ねぎ(一般的な根深ねぎより1.3〜1.6倍長く、甘みが強く、辛味・えぐみが少ない)
奥久慈しゃも(身が引き締まり脂肪が少なく、肉汁豊富で歯ごたえと旨味が特徴)
•東京都
•栃木県
•群馬県
•茨城県

軍鶏(しゃも)冷やしそば
(フリー画像より)
現時点で千葉県、埼玉県、神奈川県にはGI登録産品はありませんが、「市原の梨(千葉県)」や「八街の落花生(千葉県)」、「武州和牛(埼玉県)」、「深谷ねぎ(埼玉県)」、「三浦だいこん(神奈川県)」など、地域の特色ある特産品があります。
関東地方の産品は、都市圏に近い立地を生かしながら、それぞれの地域に根ざした特色を守ってきました。新鮮な直売や観光と結びつきやすいのも大きな強みです。
GI産品の旬と活用
GI産品の中には秋から冬にかけて旬を迎えるものが多くあります。
- 「甲子柿(岩手県)」
「伊達のあんぽ柿(福島県)」
「能登志賀ころ柿(石川県)」
「市田柿(長野県)」
「こおげ花御所柿(鳥取県)」
「東出雲のまる畑ほし柿(島根県)」
「堂上蜂屋柿(岐阜県)」 - 「香川小原紅早生みかん(香川県)」
「西浦みかん寿太郎(静岡県)」
「桜島小みかん(鹿児島県)」
「木頭ゆず(徳島県)」
「八代特産晩白柚(熊本県)」 - 「水戸の柔甘ねぎ(茨城県)」
「新里ねぎ(栃木県)」
「阿久津曲がりねぎ(福島県)」 - 「松館しぼり大根(秋田県)」
「女山大根(佐賀県)」
「わかやま布引だいこん(和歌山県)」
「山内かぶら(福井県)」 - 「淡路島3年とらふぐ(兵庫県)」
「下関ふく(山口県)(福島県)」 - 「十勝若牛(北海道)」
「前沢牛(岩手県)」
「かづの牛(秋田県)」
「米沢牛(山形県)」
「飛騨牛(岐阜県)」
「特産松阪牛(三重県)」
「近江牛(滋賀県)」
「神戸ビーフ(兵庫県)」
「但馬牛(兵庫県)」
「比婆牛(広島県)」
「くまもとあか牛(熊本県)」
「宮崎牛(宮崎県)」
「鹿児島黒牛(鹿児島県)」
◆ 柿(干し柿・渋柿含む)(秋が旬)
◆ みかん・かんきつ類(秋が旬)
◆ ねぎ類(冬が旬)
◆ 大根・かぶ類(冬が旬)
◆ 水産物(秋〜冬に身が太る・旬を迎える)
◆ 畜産物(年末や鍋需要の高まる季節に人気)
食品表示・安全との関わり
GI制度が注目される背景には、かつての産地偽装問題があります。有名ブランド名を無断使用したり、別地域で生産された食材を「本物」と偽って販売する事例が報道され、消費者の信頼が揺らいだこともありました。GIはこうした不正を防ぎ、確かな情報を保証する仕組みです。
食品安全を考えるとき、衛生や残留農薬などの科学的安全性に加え、表示の正しさや情報の透明性も欠かせません。学生の皆さんが資格取得や食品表示の学習を通じて学ぶ内容と直結するトピックスでもあり、GIは“目に見えにくい安全”を守る大切な仕組みといえます。
GIは単なるラベルではなく、「地域と食の物語」を未来に伝える知的財産です。大学としても、品質評価やブランド戦略の研究を通じ、地域の食を科学的に支える役割を担っていきたいものです。
■ 参考文献
- 農林水産省(2025年3月現在)「地理的表示(GI)保護制度とは」
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/index.html - 農林水産省(2025年3月現在)「地理的表示(GI)登録産品一覧」
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/index.html - 農林水産省(2025年3月現在)「地理的表示(GI)保護制度の概要(PDF)」
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/attach/pdf/bunkakai-141.pdf





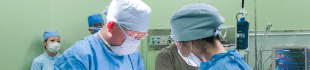








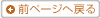

 「知久 和寛先生のバックナンバーはこちら」
「知久 和寛先生のバックナンバーはこちら」