「この一冊」 図書のご紹介


- 大学案内 About us
- 学部・大学院 Faculty Guide
-
入試情報
Exam Guide
- 大学機関 施設 University facilities
- 研究・産官学連携 Research and collaboration
- 学生生活 Student life
- 社会貢献・連携 Social Contribution and Cooperation
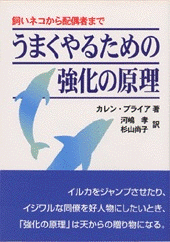
うまくやるための強化の原理
-飼いネコから配偶者まで-
-飼いネコから配偶者まで-
うまくやるための強化の原理 -飼いネコから配偶者まで-
カレン・プライア(訳:河嶋孝/杉山尚子) 二瓶社 1998年2009/1/15更新 200901号
ハウツー本のようだ。しかし何を「うまくやる」のだろう。原題「Don’t shoot the dog! : The New Art of Teaching and Training」( “犬を叱らないで!:教育と訓練の新しい方法”とでもなるだろうか)のほうが、わかりやすいかもしれない。
つまり「(例えば)犬を、叱ったりぶったりせずに、言うことを聞かせるために。」言うことを聞かない犬をぶっても、あまり効果がないのは何故か。そして、どうすれば「言うことを聞いてくれる」のか。
ハワイの海洋水族館で十年間イルカのトレーナーを勤めた著者が、実例をあげながら説く。相手に「こうしてもらいたい」「こうしてもらいたくない(やめさせたい)」行動が、例えば「投げたフリスビーを犬に持ってこさせる」「猫が食卓に乗るのをやめさせる」「夫に脱いだ靴下を片付けさせる」「社員がサボるのを防ぐ」等、具体的に示され、それらを「どうすればいいか」が、わかりやすく書かれている。
もちろん、実際にできるかできないかは別の話だ。
著者が説明する「グレードは少しずつ上げる」「別の方法も試す」「訓練の切り上げ方」などの手順。「ご褒美」と「罰」の違い。行動させるための「刺激」や「動機」、行動をさせないための「ネガティブな方法」と「ポジティブな方法」。いちいち納得させられるのだが、おそらく実行は簡単ではない。
何故なら、人間、叱ってしまったほうが楽だからだ。
著者もそれはわかっていて、指摘している。「相手を叱ったりぶったりするのは、本当は相手の行動をあらためる手段と言うより、復讐に近いのではないか」もしくは「優位に立ちたいがためではないか」、と。
あるイルカの研究者の言葉「ニワトリを訓練した経験のない人は、赤ん坊を持つべきではないよ」について、著者はこう解釈する「ニワトリを訓練したことがあれば、生き物は力で強制できないことがわかる。」ただ怒鳴りつけるだけでは、相手は「怒鳴られずにうまくやる」事だけ覚える。決して一度に幾つも求めたり、気まぐれに命令を変えたり、やたらと罰を与えてはいけない。鬱憤晴らしや空威張りのための行為でないからだ。
本書が言いたいのは、訓練とは、相手の気持ちを考え、根気よく、よく観察しながら行うべきであること、それは信頼関係の構築に他ならないということである。
印象的なのは、次の一節。「成功したとしても、実際にその困難な仕事をしたのは誰なのだろうか? 本人(相手)である」。
誰かを操作するハウツー本ではない。これはコミュニケーションについての一冊である。動物に限らず、子供や、親や、夫や妻や、部下や友達や、そして自分自身との。
図書館 司書 関口裕子









