「この一冊」 図書のご紹介


- 大学案内 About us
- 学部・大学院 Faculty Guide
-
入試情報
Exam Guide
- 大学機関 施設 University facilities
- 研究・産官学連携 Research and collaboration
- 学生生活 Student life
- 社会貢献・連携 Social Contribution and Cooperation
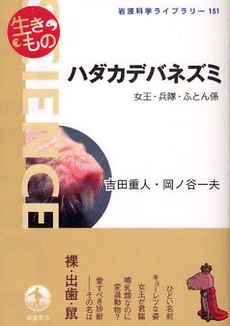
岩波科学ライブラリーは、電子資料閲覧室前に並んでいる、談話室側から2列目にある書架にあります
(分類は408 I-1)。
知る人ぞ知る名物シリーズ。「コンピュータは名人を超えられるか」「魔球をつくる」「和算小説のたのしみ」など、タイトルだけでもそそられます!
(分類は408 I-1)。
知る人ぞ知る名物シリーズ。「コンピュータは名人を超えられるか」「魔球をつくる」「和算小説のたのしみ」など、タイトルだけでもそそられます!
ハダカデバネズミ~女王・兵隊・ふとん係
吉田重人・岡ノ谷一夫(岩波科学ライブラリー151 2008年)2009/4/1更新 200906号
『あんまりな名前』という本でみつけたのである、このあんまりな名前を。
聞いた瞬間、インパクトでヘッドが回転しそうな名前“ハダカデバネズミ”。だが決して、イワレのない中傷ではない。このネズミは本当にハダカ(無毛)で出っ歯なのだ…いや、事実とはいえこれほどハッキリ名前にするのもどうかとは思うが。
この程度で驚いていてはいけない。群れに君臨する女王デバ(さぼっているヤツをどやしてまわる)、彼女に仕える王様デバ(女王様が、ヘイ、カモン!と言ったら馳せ参じる雄デバ達。痩せ細るほど苛酷な労働らしい)、そして下々の兵隊やワーカーデバ達(ベイビー達をあたためる肉ぶとん係もいる。なんせハダカですから)で構成される彼らの生態を読んでいくうちに、きっとあなたも彼らのとりこになるに違いない。
が、しかし。なぜこのデバ達を研究するのか、という本題の説明も興味深かった。
よくテレビのクイズ番組で、解答のあとに「では、○○についてお詳しい××大学の△△先生にお聞きしましょう」というような談話が紹介されたりするでしょう。あれを見てときどき思いませんか「…なんでこのセンセイ、こんな研究してるんだろう…」。
本書の著者のひとり・岡ノ谷一夫という先生には、岩波科学ライブラリーでもう一冊著書がある。『小鳥の歌からヒトの言葉へ』というのがそれで、これも大変面白かった。小鳥の歌を研究することが、例えば脳の学習機能を掘り下げるキッカケにならないか、脳損傷により言語を失った人へのリハビリ方法などがわかるのではないか-というような研究である(注:ごくかいつまんで書いております)。
ハダカデバネズミも、これに関連する。真っ暗な地中で生活するデバ達は、17種類もの音声を使い分けてコミュニケーションをはかっているらしいのである。何が、どのように伝えられているのか。「極端にへんな動物の極端にへんな行動」を研究するのは、実は重要なのだそうだ。だって、そこには「理由」があるはずだから。
すごい。デバ語(?)の研究が、人間を救うかもしれない。そしてデバの輸入から飼育環境の設定、実験道具の作成まで、みーんな創意工夫の末の肉体労働である。デバ飼育キット、なんて売ってないもんなぁ。「研究」というと、キレイな実験室でぴかぴかのキカイとキザイを使ってやっているのを想像するけど、ゲンジツはきびしいんだ…。
大学の研究室って、いったいどんな感じなのか。本書は、そういう素朴な疑問への答えをちらっと見せてくれる一冊でもある。院生や学部生の活躍ぶりも涙ぐましく、春から新入生となる理化学系大学一年生の方々にも、おおいに参考になることだろう。勿論、デバにのみ注目してもよし! イラストも必見。ぜひ「たれぱんだ」みたいな絵本にしてほしい。
図書館 司書 関口裕子









