「この一冊」 図書のご紹介


- 大学案内 About us
- 学部・大学院 Faculty Guide
-
入試情報
Exam Guide
- 大学機関 施設 University facilities
- 研究・産官学連携 Research and collaboration
- 学生生活 Student life
- 社会貢献・連携 Social Contribution and Cooperation
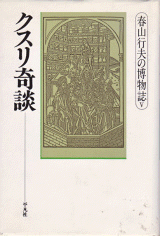
分類番号は499.02。図書館を入って正面の階段の、左側書架群にある。こちら側の本をあまり紹介していなかったので、これからはちょっと重点的に。
クスリ奇談 春山行夫の博物誌V
春山行夫 ( 平凡社 1989年)2009/10/1更新 200918号
奇談というか、雑談というか、およそ役に立たなさそうだけど珍しいことは珍しい、という話を集めた、まさにトリビア本というしかない本。奇談というより、奇書?
本書によると、世界最古のクスリの記録は紀元前2700年頃のシュメール人の薬方書とのことである。書、といっても粘土板で、書かれている文字は楔形文字。しかし薬方の基本は植物(桂皮樹など)や動物(例えばヘビの皮)、鉱物(塩に硝石)で、それなりに筋が通っている気がしなくもない。乾燥させたり粉末にしたりして保存し、膏薬(外用薬)や内服薬にしたりするのも現代と同じ。その薬方を残した医者の名前はちょっと笑えて、なんと「ルル」。風邪薬が専門じゃないだろうな!
もちろん呪術とか占いとか、迷信とか、毒薬とか奇跡とか、とかとか、いかにも禍々しくエキゾチックな話も沢山出てくるので、そのテの話が好きな方にはオススメである。ハリポタシリーズでおなじみの、土から引き抜くと恐ろしい悲鳴をあげ、それを聞いた人間は狂死するという、迫力満点のあの薬草(マンドラゴラ、あるいはマンドレーク)や、見た人間は石になってしまうというヘビの王・バシリスクもちゃんと登場する。
そういった、民俗学的・歴史探求的・クダラナサ爆発的興味を満たしたあと、しかしふと、別の感慨も持つのである。
本書を読んでいると、頭痛薬や下剤はおろか、歯磨き粉、強壮剤、育毛剤すら、すでに古代エジプトから登場しているのである。ミイラには虫歯に金冠を被せたものや、入れ歯さえ発見されると言う。
また、特定の産地の粘土には薬効があると信じられていた、というと奇妙に聞こえる。いかにも古代らしい。が、その区別をつけるために粘土に印章を押していた、というと途端に現代っぽくなる。つまり「商標」がついていたわけだ。ギリシアのシバリスという町では、特別な料理法を考え出した者は一年間真似されない特権が与えられたらしい。これも「特許」のハシリと言える。人の営みというのはそれほど変わっていないのである。特許も商標も何やらシステマティックで人工的なものに聞こえるが、つまりは必要性から誕生した、極めて人間的な、レトロ~な考えだったわけだ。
緑色を見ると目が休まる、という説も、ギリシア・ローマ時代からすでにあったそうだ。
こういう本があるのが図書館の醍醐味である。マニアックで、持っている人が殆どいない。古すぎて書店にはもう無い。アマゾンでも古本が出品されているだけ。そんな本も、図書館にはヒッソリとだがしかし堂々と新刊と肩を並べている。
乾燥した晴れ続きの秋の図書館で、いつもと違う手に鞄を持ち、左足から館内を歩くとこのテの本に出くわすそうです(←嘘!)。
図書館 司書 関口裕子









