「この一冊」 図書のご紹介


- 大学案内 About us
- 学部・大学院 Faculty Guide
-
入試情報
Exam Guide
- 大学機関 施設 University facilities
- 研究・産官学連携 Research and collaboration
- 学生生活 Student life
- 社会貢献・連携 Social Contribution and Cooperation
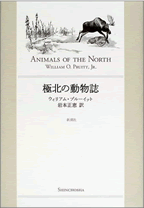
分類番号は482.5。写真家の星野道夫氏は、本書を宝物のように思っていたそうだ。彼の著書『ノーザンライツ』を読んで本書を探す読者も多いことだろう。珠玉の一冊とは、このような本のことを言うのである。復刊して!
極北の動物誌
ウィリアム・プルーイット:岩本正恵 訳( 新潮社 2002年)2010/3/1更新 200923号
当館に司書として勤めていながら、本書に気づかずにいたとは! 呆然とするほど素晴らしい一冊である。
原題はそのまま”ANIMALS OF THE NORTH”。15ほどの章に分かれており、ハタネズミ、ノウサギ、カリブー(ツンドラトナカイ)、ムース(ヘラジカ)、先住民のディンジェ族、オオカミ、イタチなどが主人公として次々登場する。主に、彼らの四季が描かれる。それだけと言ってもいい。
が、そこに広がる世界はどうだろう。
アカリスがトウヒの幹をまっさかさまに駆けおり、駆け上がり、地上15メートルで揺れる枝を走りぬけ、虚空にジャンプする。雪にもぐったハタネズミが、体を揺すって雪を固めている。ヤナギランを食べて満腹になったノウサギが、自らの耳を顔前までひっぱって毛づくろいしていたと思ったら、ノウサギに飛びかかったオオヤマネコの子の頭上に、巨大なムースが足をふり上げるのを見て息をのむ。
すべて筆者の目の前で繰り広げられる。電車の中であろうと、カウンターの中であろうと、ページを開けばそこはパノラマの異世界だ。四季が周囲でめまぐるしく移り変わる。これを至福の読書と言わずして、何と言おう。
まず文章がいい。北の空気のように静謐な筆遣いである。そして構成が巧い。滑走するアカリスからカメラが切り替わるようにハタネズミの地上の世界に移り、彼らの匂いを嗅ぐノウサギを映し、そしてノウサギを狙うオオヤマネコに…と、すべてが連鎖している。まるで生態系のように緻密だ。
しかし、それだけに、そこに侵入する異文化―白人たちが異様で、無慈悲で、まさに「不自然」なのが歴然としていて恐ろしくなるのだ。読んでいて、時々殴られたようなショックを味わうのは、時に残酷な自然界の摂理にだけではない。人間にだ。動物と大地を追ってページをめくっていた読者が慄くのは、人間の姿になのだ。
「気温が上がると」雪が降る!という極地。太陽エネルギーが極端に少なく、植物は限られ、その結果住み暮す動物も脆く精密な連鎖の中で生き延びている。いったん壊されてしまうと容易に蘇らない。エコロジーを唱えるならば、まずはこういった事を知るべきなのだ。一流の映画監督と脚本家とカメラマンを一冊に閉じ込めたような本書こそ、絶好の入門書となるだろう。なのに! 絶版?! 眩暈がする。アマゾンを見ても大型書店の在庫検索をしても出てこない。本書まで絶滅してどうする! 図書館で保護されているうちに、なるべく沢山の方に読んでいただきたい。極北も、地球上のあるべき姿のひとつなのだ。寒い世界も必要なのだ。冬季オリンピックが賑わっているのは今だけかもしれないのだ。
図書館 司書 関口裕子









