「この一冊」 図書のご紹介


- 大学案内 About us
- 学部・大学院 Faculty Guide
-
入試情報
Exam Guide
- 大学機関 施設 University facilities
- 研究・産官学連携 Research and collaboration
- 学生生活 Student life
- 社会貢献・連携 Social Contribution and Cooperation
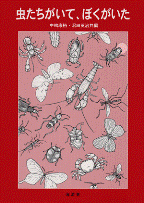
分類番号は486。研究者同士が、どんな風にアイディアを出し合っていくのかもわかる貴重な一冊。それに、仮定とデータとの間をどう詰めていくか、ストーリーをどこまで描いていいのか、見極める姿勢もそれぞれビミョーに違って、そこも面白いんだな。
虫たちがいて、ぼくがいた
中嶋康裕・沼田英治 共編 ( 海游舎 1997年)2010/10/01更新201013号
博物館とか歴史館とかナントカ館とかの学芸員の方々がお仕事について語るのだが、ひとくちに学芸員と言ってもですね、お勤め先によって内容がゼンゼン違う。個性的な仕事が多くて、面白かったんだよなぁ。水族館に勤めて海岸動物を調べ始めた方もいれば、郷土資料館で土器を接合する方もおり、お城に勤めて毎日天守閣に「登城」している方もいる。
何も、スーツ着て出社してタイムカード押してパソコン叩くだけが仕事じゃなく、世の中いろんな仕事でまわっているんだなぁ、と実感できる本を読むのは、なかなか楽しい。
この『虫たちがいて、ぼくがいた』は、その究極といっていい内容じゃないだろうか。
18人の研究者が、昆虫や甲殻類など「虫」的なものについて研究してきた「これまで」を、淡々と語ったというか、つぶやいたというか、そういう本だ。あ、タイトルには「虫たち」とあるが、カニやエビを研究してる方まで出てきちゃっている。彼らの共通点は、日高敏隆氏という動物行動学の草分け的研究者と接点があったこと、らしい。
確かに本文をそれぞれ読むと、ナニを、どう研究するかという決断のときなどに、ふと日高氏が登場する。そういう意味では、18人は、方向は違えど時間差で同じ交差点を通った人々のようなもので、その、そこはかとない縁もちょっと粋だ。
しかしねー、動物行動学って、ホントに大変で、おもしろそうですよ。
「動物の行動」の「研究」ですからね。まずその動物を確保しなきゃならない。春に大学構内の畑を耕しキャベツを植える方もいらっしゃった。何のためかって、アオムシが欲しいからで、なんで欲しいかって、寄生バチに寄生してほしいからなのだ。そう、研究しているのは寄生バチなのだ。そのためのアオムシで、そのためのキャベツなのである。
研究のためにカナヘビやヒキガエルをせっせと育てる方もいた。マイマイガを研究し続けて、アレルギーになっちゃった方まで登場する。
そしてその研究は(たとえば観察は)だいたいにおいて季節限定である。その対象動物が活動している時期だけだ。ヤエヤマヒメボタルなど、1日に20分しか光らないそうだ。
それら難問に知恵をひねり、時には泥まみれになり汗だくになって準備して、観察するのは「ボーイ・ミーツ・ガール」な繁殖行動(考えてみれば大きなお世話な観察かも)だったり、「いただきまーす」な摂食活動だったりするわけである。「おいしくない虫(この場合、ミノウスバの幼虫)をいったん食べたウグイスは、似たタイプの虫を食べなくなるのではないか」という仮説を証明するために、ウグイスの好物のミールワーム蛹の背中に、油性ペンでミノウスバ幼虫と似た模様をひとつひとつ書く、というくだり(第2章の「ミノウスバの体色の意味」)など、ためいきがでた。す、すごい…。
内容は「甲虫」「チョウとガ」「ハチ」「ユスリカ」「カメムシ」「カニやエビ」の6部に分かれている。それぞれ2~3章ずつ。実験の仕方や結果からの考察の過程も詳しく書かれているし、巻末には「もっと知りたい人のために」として、日本語・英語の参考文献も載っていて、ここからさらに興味を育てられるように仕掛けてある。
なお、ところどころに「虫屋(ちっちゃい頃から虫が好きっ子)出身の研究者」と「そうでない研究者」の違いが垣間見られる。どちらにも長所と短所がある。18人もいると、研究に対するスタンスも性格も違ってくるので、それらを時に較べつつ、素人でも楽しんで読める、珍しい「虫との一冊」である。
図書館 司書 関口裕子









