「この一冊」 図書のご紹介


- 大学案内 About us
- 学部・大学院 Faculty Guide
-
入試情報
Exam Guide
- 大学機関 施設 University facilities
- 研究・産官学連携 Research and collaboration
- 学生生活 Student life
- 社会貢献・連携 Social Contribution and Cooperation
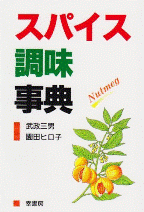
分類番号は596。二階の参考図書にはハーブの事典もある。フェネル=ウイキョウ、ナツメグ=ニクズク、ペルラ=紫蘇だったのね。『ふたりのロッテ』を読んだとき、「ニクズクをおろす」って何だかわからなかったけど、謎が解けました~。
スパイス調味事典
武政三男・園田ヒロ子 ( 幸書房 1997年)2010/10/15更新201014号
食い意地のはったわたくしは、よせばいいのに今日も新レシピにトライする。が、ふいに唖然としたのであるよ。なんだ、この溢れんばかりのスパイスの量は!
瓶が棚に並び切れずに見苦しい。パプリカが二つあったことは更にナイショだ。
おそらく、レシピを見て買ってくるものの、他の料理では使いきれないままキッチンカオスに呑まれてしまったのだ。とほほ、これではいかんよ。
そして借りてきました、この一冊。
第一章が「スパイス利用の基礎知識」。オールスパイスを皮切りに、各スパイスの名称や原産地、形状、名前の由来、そして香味の特徴(精油・粉末など状態によって違う)、料理の適性(何料理、そしてどこの国の料理に合うか、など)、健康への効果、その他歴史上のトピックなどエピソードを載せている。
細かい。字ばっかり。読むのはめんどくさそう。
が、お目当てのページから読みすすめてみると、けっこうイケる。使えそうではないか。
レシピを見て、そのスパイスが「何のため」であるか即答できますか(私はムリ)。例えばサフランの主な役割は料理を「美しく黄色にするため」で、香りはあまり重視されず、倍使っても色はたいして変わらない、と知っていれば、自然と適量を使うだろう(ついでに言えばサフランの原料ってクロッカスのお仲間だったのね…)。ブラックペパーとホワイトペパーの違いとかね。あ、ブラックペパーは香り重視なら仕上げに使い、辛味目的なら下ごしらえか調理中がいいそうですよ。オニオンパウダーを塩やペパーと混ぜて「オニオンソルト」にするとテーブルスパイスになるそうなので、もらいもののパウダーも捨てなくていいみたいです。
すごい。これって知識が生活を豊かにしてくれるっていうやつ?
スパイスは、本来の腕より料理を美味しそうに(!)してくれる。それに味をしめるとつい大量に使っちゃうが効果を知らなければ無意味だ。でも上手に使って風味を楽しみたい。外国っぽい雰囲気も手軽に出して、料理上手と言われてみたい。そんなアナタは買ってしまった生ハーブがクタクタになる前に、本書をそっと開いてみよう。各スパイスのページの最後には「参照レシピ頁」がある。そう、本書の第二章はレシピ集である。
レシピも文字ばっかり。でも簡単でーす。「アサリのマサラ風味蒸し」なんて蒸せばいいだけだが、たぶんこのとおりにスパイスを使えばお客さんにも出せる。ペペロンチーノもそう。ラタトゥユもそう。「ナスのオレガノ風味焼き」はめちゃめちゃ美味しそうだ。「いちじくのコンポート」や「干し柿のデザート」など、甘味好きの方にもオススメ。
絵も、写真もありまっせん。モノクロ! 字だけ!(あ、調理適合パターンという図も各スパイス解説についてます。) 営業努力はちょっと足りないかも。
でも、そういうホンなのです。見た目は地味でもとても味があって、香り高い、そう、スパイスみたいなホンだと思ってください。
図書館 司書 関口裕子









