「この一冊」 図書のご紹介


- 大学案内 About us
- 学部・大学院 Faculty Guide
-
入試情報
Exam Guide
- 大学機関 施設 University facilities
- 研究・産官学連携 Research and collaboration
- 学生生活 Student life
- 社会貢献・連携 Social Contribution and Cooperation
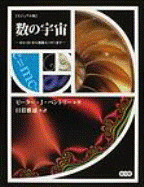
分類番号は410。映画『武士の家計簿』を見ても、数学に夢中になることはとても楽しそうなのである。本書にはそんな喜びがある。『BANANA FISH』のアッシュが口にしたフィボナッチの数列や、『容疑者Xの献身』に登場した四色問題も出てきてニヤリ。
【ビジュアル版】数の宇宙-ゼロ(0)から無限大(∞)まで-
ピーター・J・ベントリー 著 / 日暮雅通 訳(悠書館 2009年)2011/06/15更新201111号
もちろん、あらゆる定理や理論は数式、もしくは言語、またはグラフィックなどになるのだろうが…でも「数」は本来、概念であって、目に見えないモノじゃないのか?それの「ビジュアル本」ってアリなのか?
が、実際にページを開いて見れば、そこには筆者には想像もつかなかった、色彩豊かな世界が広がっていたのだった。
これほど退屈しない本も珍しい。「友愛数」や「無理数」、「Φ(ファイ:黄金比)」、「対数の底(e)」、「π」などといった<題(テーマ)>もさることながら、それを語る<文(あや)>と<彩>はまばゆいばかりである。CG画像もあるが、登場する人物の肖像画、名場面を描いた絵画などが「よくぞ集めたり」という位載せてあって、それらを駆使して説明される数学が、筆者のような素数さえアヤシイ人間にも魅力的に見える。
数学が、歴史的にニンゲン的に、劇的に面白いのである。
しかしあるひとつの問いに対して、時には二千年も経て答えが見つかることに胸が熱くなる。間違いなくそこにはある種の会話がある。疑問というのは(言い換えれば真実の追究というのは)力強いものなのだ。と同時に、「これは証明できるのか?」という世紀の難問を考えつくのも、考えつかない人間にとっては天啓のように神々しい。
が、大きすぎる疑問は人生をも壊しかねない。問い続ける生き方はとてつもないエネルギーを必要とし、その答えは社会的概念すら覆すことがある。本書を読んでみるがいい。狂気、弾圧、追放、栄光、達成、シェイクスピアのような悲劇と勝利のオンパレードだ。
すごい、すごい、すごい(本書によると、フレーズを3回繰り返す歌が多いのも真実のひとつらしい。『ロンドン橋』も三回落ちる)。
もっと昔、まだ次々と本を買うオカネはないがヒマはたっぷりあった頃(アマゾンドットコムも、DSもケーブルテレビもない頃だ)、こういう本を読みたかったなぁ。多少意味が難解でも、子どもって難しい単語を想像で補いながら、結構読んじゃうものだ。ゆっくり何度でも、すみずみまで読んだろう。ニュートンやアインシュタインなどのドラマティックな人生については特に念入りに楽しんだに違いない。だんだんにジョルダーノ・ブルーノといった聞いたこともない人物の悲劇にも惹き入れられるようになる(そしてp.222のブルーノのクラい全身像などが脳裏に焼きつく)。やがて、アルキメデスがつくったビックリ兵器の絵にツッコミを入れたり、マンデルブロー集合で作られた絶世の美図形に息をのんだりする頃――それまで飛ばし読みしていた肝心の数学理論やパラドックスに、一つずつ、魅せられていったことだろう。「無限大に対して、ほかの無限大と比べて大きいだの小さいだのと言うことは可能なのか?」という『ガリレオの円』に、今になって感心しているように(まったく、この方面にクラいと今でも子どもみたいに驚けるので便利である)。
本書を傍らにウィキペディアしたら面白すぎてキリがなかろう。天文学者ケプラーの書いたSF『夢』に出てくる月世界なんてゾクゾクしたぞ。読了後、スティーブン・キングの『ダークタワー』シリーズを大人買いする読者がいることには賭けてもいい。
この宇宙は無限大に近くとも、無限ではないそうだ。が、想像力に限りはなく、知的好奇心をキープする方法を見つけられれば、永遠に遊べる。本書は確実に手を引いてくれることだろう。ご堪能あれ。
図書館 司書 関口裕子









