「この一冊」 図書のご紹介


- 大学案内 About us
- 学部・大学院 Faculty Guide
-
入試情報
Exam Guide
- 大学機関 施設 University facilities
- 研究・産官学連携 Research and collaboration
- 学生生活 Student life
- 社会貢献・連携 Social Contribution and Cooperation
図書館TOP > 「この一冊」 一覧 > 「この一冊」 - 図書の紹介- 201112号 | 「ハーバード白熱教室 Harvard University’s JUSTICE with Michael Sandel」
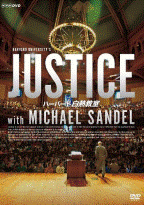
分類番号は311.1。映画『キューティ・ブロンド』で、主人公のエルがビキニ姿でアピールする「ビデオ論文」を送りつけ、「本学は多様性を重視しているから…」と入学許可されたのがハーバードのロー・スクール。この「多様性重視」の入学についてなど、現代アメリカのさまざまな事がわかるのも本作の魅力だ。
ハーバード白熱教室
Harvard University’s JUSTICE with Michael Sandel
( NHKエンタープライズ 2009年) *DVD7枚組
2011/07/05更新201112号
オンエアでご覧になった方々は、この思わず惹き込まれるような面白さをよくご存知の筈。当館にも入りましたよ!とお伝えするだけである。が、評判は聞いたが観なかった、または知らなかった、と仰る方々のために、今更ながら書いてみたい。
ハーバード大学の講義風景を、ほとんどそのまま公開した大ヒット番組である。内容は「政治哲学」。この怖ろしげな名前を聞いて「フムフム、例えばロールズかね?」とか即答される方は少数だと思うのだが、本国でも日本でも大反響を呼んだ。サンデルの『これから「正義」の話をしよう』がベストセラーになったのは記憶に新しい。
あえて言おう。本作を堪能するのに、政治哲学の知識は必要ない。
それでも、もっと観たくなるはずだ。
まず、オペラ座ばりのホールが映し出される。千人以上集まった、このサンダース劇場はすり鉢型で、舞台上の教授を学生が見下ろす格好である。クラシカルな内装がまばゆい。
サンデルはそこで学生に疑問を投げかけ、手をあげた学生を指名する。
「キミは暴走する路面電車の運転手だとしよう。今にも目前の五人の人間を轢きそうだ。待避線にハンドルを切れば五人は助かるが、そこにも一人いる。どうするかね?」
学生はマイクを使って答える。それに反論のある学生をまた指名し、彼らの答えからサンデルが講義を進める…これが「対話型」と呼ばれる講義形式である。
特筆すべきはサンデルが一度も「キミは誤っているね」などと言わない事だ。「キミが言ったのは、要するにこういう事だと思うが、それでいいかね?」と言うだけだ。
そうだろう。言うまでもないが、今日の社会はカオス的に多様化していて<正義>の定義も難しく、さくっと正解が出るような問題ではないのである。
だからこそ、自分の主張の内容を理解し、相手の主張も尊重しなければならない。
そのために、サンデルはあえて身近な例を引き、学生に「自分の言葉で」是非を表現させ、次第にその背後にある(無意識の場合もあるだろう)思考にたどりつかせる。多数派の幸福のためには少数派は我慢するべきなのか? クリントンの言い逃れは嘘と同罪なのか? 自分が稼いだものはすべて自分のものなのか??
これらのやり取りを取り入れながらジョン・ロック、カント、ロールズといった歴々の哲学も語られる。知識がなくても大丈夫、と太鼓判を押したのはこのためである。
それにしても興味深い。サンデルの主張については著書等で知っている学生も多いはずだ。が、たとえ反論でも堂々と述べる。この講座にはブログもあり、サンデルが「キミがアレックスか! この講座のスターだな」と呼ぶような論客もいて、そういう意味では今流行りの視聴者参加型の連ドラのようだが、プラス、即興劇の興奮もあるのだ。
観ているうちに、ふだん何気なく思っていることの意味に気づかされ、ヒンヤリしながら、刺激的な展開にぐいぐい引っ張られていく。「うん、いい着眼点だ。キミの名前は?」「パトリック」「パトリック、そこにいてくれよ。さぁ、反論は誰かいるかい?」この臨場感はどうだろう。多様な学生が多様な意見を交わすこの講義は、重要なのは言い負かすことではなく、対話なのだという姿勢も含めて、ちょっとないほどに小気味いい。
永遠に最終解答が出なくとも、話し合いは続けねばならない。そう、皆様もご存知のとおり「あきらめたら、そこでおしまい」なのである。
図書館 司書 関口裕子









