「この一冊」 図書のご紹介


- 大学案内 About us
- 学部・大学院 Faculty Guide
-
入試情報
Exam Guide
- 大学機関 施設 University facilities
- 研究・産官学連携 Research and collaboration
- 学生生活 Student life
- 社会貢献・連携 Social Contribution and Cooperation
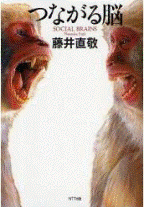
分類番号は491.371。 <理系文バージョンアップ型>の文体もこうやって読むと興味深い。「サルのデフォルトのモード」とか「サルについての下位互換性をもっていない」とかね。 最終章を読んでから『ハーバード白熱教室』を観ても面白いかも。
つながる脳
藤井直敬( NTT出版 2009年)2011/10/01更新201118号
小欄の筆者はド素人なりに、ヒトの脳は凄いと、コンピュータープログラムをつくった時に実感した。たとえば「名前を記録する」というプログラム。コンピューターは「名前」を認識なんかしていない。決められたエリアに入力されたものを、データに入れるだけだ。間違えて「住所」欄に名前を入れたら、それは住所としてしまうだろう。
ヒトならば小学生でも「あ、住所欄に名前が入ってる」とわかる可能性大である。たとえそれが「フクロウバラ ネコヒコ」とかいう変わった名前でも。
こういう際立った応用力で、脳は「空気を読む」という難事まで通常業務としてこなしている。字面だけあらためて読むと、殆どニュータイプかフォースか超能力の範疇である。さまざまな条件が織りなす微妙な「空気」を、言葉にできない段階から認識・分析して、瞬時に態度を決めているのだ。
著者の藤井氏が挑んでいるのは、そういう領域の研究だ。よく耳にする「脳・単体の、どこかの機能を調べる」のではない。だからどの実験も型破りで、ユニークなのだが、では、本書はそれら脳科学の内容についてのみ、縷々、書かれているのだろうか。
そんなありふれたものじゃないから、ここに持ってきているんですよ。
藤井氏は、アメリカで研究をされていた。MITに所属し、37歳でめでたく『サイエンス』に論文が採り上げられている。
正直に書かれているが、「これで何かが変わる筈だ」と大きく期待されておられたそうだ。
そして、何も変わらなかった。
氏は逡巡の末に帰国し、あらたな研究テーマを模索して、やがてここに辿り着いた。
この経過が書かれているのには、意味があるのだろう。よくよく読み返してみよう。
氏が追求する「社会構造を読み解く能力」、「脳の社会性」。未知の脳の可能性に迫るために、従来には無い工夫を凝らす実験過程のみ読んでも、本書は抜群に面白い(サルの道具に対する認識や、脳内カプセルや、山ほど書きたい)。あらかじめ結果を決めてかかっていないだけに、説明の過程にも臨場感がある。どこに行くかわからない面白さがあるのである。
が、最終章で待っていたのは、その脳がつないでいる「ヒトとヒト」についてだった。
カネの捉え方、幸せの定義。誰かの役にたちたいという感情。これら永遠のテーマについて、本書独特の「です・ます」体の、そこで話しているかのような文体で語る。おもしろおかしい似非科学的説明について強い疑問を持つ氏が、こういう普遍的な命題に迫るからには、科学的に真剣だ。
思えば氏が脳の社会性に興味を持ったのは、氏自身が他者の視線をいつも意識しているからだったという。アメリカで活躍し、率先して共同研究のネタ探しをしたという氏でも、コミュニケーションについて思うところがあるのだ。トップジャーナルの論文が「つながらなかった」こと、脳科学についてうまく伝わらないこと、漂う閉塞感を打ち破りたいと思っていること…氏が目指しているのは科学者の自己満足でも身内の賞賛でもない、言ってみれば「社会性を持った研究」「つながる科学」なのではないだろうか。
脳科学研究の現況についても独自の視点から斬りながら、一人の科学者が、限りある可能性を賭けて前進する過程を、自ら語った本書。ハデなキャッチフレーズで煽るアヤシイ類いの本ではない。脳科学ってほんとのところどうよ、と思い始めた人こそ、ぜひ。
いや、こんな本が面白くないわけがないでしょ。
図書館 司書 関口裕子









