「この一冊」 図書のご紹介


- 大学案内 About us
- 学部・大学院 Faculty Guide
-
入試情報
Exam Guide
- 大学機関 施設 University facilities
- 研究・産官学連携 Research and collaboration
- 学生生活 Student life
- 社会貢献・連携 Social Contribution and Cooperation
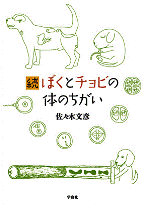
分類番号は481.1。質問したい盛りのお子様をお持ちの親御さん、手軽にきちんと知識を得たいという健康志向の方、クイズや飲み会向けのウンチクをお探しの方、自分の知識に不安がある(筆者のような)オトナなどにもオススメ。カバー裏には著者愛犬のウズ君の姿も。
続 ぼくとチョビの体のちがい
佐々木文彦 (学窓社 2008年)2011/10/17更新201119号
「ぼくとチョビの体のちがい」の続編である。前作では体、頭、脊柱、耳、目、筋肉、皮膚、生殖器、消化器、歯について書かれていた。では、本書の時間割は。
1時間目:呼吸器、2時間目:循環器系、3時間目:歯、4時間目:消化器、
5時間目:泌尿器、6時間目:神経、7時間目:細胞、8時間目:内分泌
2冊合わせれば教科書的にも使えるよ、とのこと。えっ、これってテキスト? じゃぁ 気軽には読めないんじゃ…と危惧された方、心配ご無用です。著者によると、本書の対象は「人・動物の医療を学ぶ学生はもちろん、一般の犬好きの方、小・中学生」だそうで、それは文章を見ればイッパツでわかる。専門用語も登場するが、それらがスムーズに頭に入ってくるように、イラストを多用し、語り口も平易に抑えている。
「どうして心臓に動脈が分布しなければならないの?」「犬でも心筋梗塞はあるの?」「あなたが帰宅したときに愛犬の心臓の鼓動は増える?」など、興味深いテーマを追っていくうちに、血管のしくみや皮静脈の意味などもわかるというわけ。愛犬だけでなく自分の健康のためにもなるんじゃないかな? 『いちばんやさしい生理学の本』を読んだときにも思ったけど、正しい知識というのは健康への大きな味方である。「犬は歯槽膿漏になりにくい?」という部分を読んで「そっかー、人間は歯槽膿漏になりやすいハズだわ(歯を磨かなくちゃ!)」と納得しましたよ。
でも、なんだかお子様向きっぽくて、大人や学生には適さないんじゃ、という心配もあるかと思うがそれも考え方次第。もちろん正確で詳細な記述がギッシリ詰まった専門書は頼もしいが、何しろそうなると読むべき量もハンパじゃない。それらをなんとか詰め込んでも、本書を開いてみたら「そういえばこの部分は結局どうやって動いているんだっけ…」と不安になったりすると思う。そんな、豊かなヒントがいっぱい詰まったこの一冊は、今日も誰かに借りられていく。
本書の大きな勝因は、これが「犬」で書かれていることだ。犬ならば、飼っていない人でも、その仕草や体つきをだいたい知っている。舌を出して「ハッハッ」と息をしたり、雄犬が片足を上げておしっこをしたりしているのを、誰でも一度は見たことがある(例えばワニならこうはいきません)。
さらに、犬と人とを比較することで「なぜ、こういう仕組みになっているのか」ということがわかりやすくなる。「犬は嘔吐しやすい?」(p.81)など、両者のイラストを並べてあって、秀逸! さらにさらに、犬が嘔吐しやすいのは狼のときの影響というトリビア付きで、こういったさりげない記述もポイントが高いのではないだろうか。
本書のような「一味ちがう視点」は、もっと注目されてほしいところだ。前作は、小・中学校指定図書に推薦されたということで、グッド・ジョブ! いいセンスである。
ちなみに、個人的にいちばん「そうなのか!」と思ったのは「ケーキのための別腹って本当にあるの?」という部分(p.118)。これが別腹です、というイラストを見たときは素直に感心した。これは「犬にも別腹はあるの?」に続き、犬の体重のコントロールのためには飼い主の工夫が必要!ということがハッキリ説明されている。おぉ。これらは覚えておかなくては。いや自分のためにも…別腹あるんだし…これからご飯美味しいし…。
図書館 司書 関口裕子









