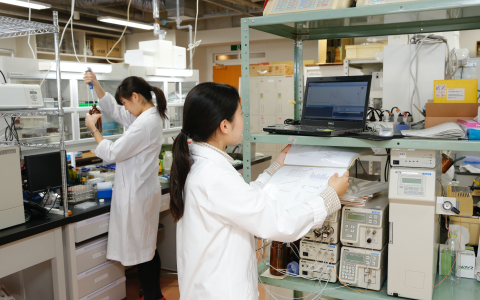「この一冊」 図書のご紹介


- 大学案内 About us
- 学部・大学院 Faculty Guide
-
入試情報
Exam Guide
- 大学機関 施設 University facilities
- 研究・産官学連携 Research and collaboration
- 学生生活 Student life
- 社会貢献・連携 Social Contribution and Cooperation

鼻の先から尻尾まで 神経内科医の生物学
岩田誠 (中山書店 2013年)
2015/10/14更新201510
いやぁ、笑った。和やかなトーク的文章で、けっこう専門的な内容をスルスルと読まされてしまったが、所々に「ウケる」ポイントがある。第28話なんてケッサクだ。「脊椎動物の体肢は2対4本。昆虫は3対6本の足と、2対4本の羽で計5対10本。これが自然界の常識。だからギリシア神話のケンタウルス(2対4本の足と1対2本の手)やキリスト教の天使(2対4本の手足に1対2枚の羽)には違和感をおぼえて仕方ない」というくだりである。「なにも分類しなくてもいいのだが」とご自身でお認めだが、まったくもってそのとおりである(牧羊神パンはヤギの下肢にヒトの上肢で2対4本、仏教の迦陵頻伽も1対の翼と1対の足なので、どっちも違和感がないそうだ)。そんな先生にとってさらなる驚異は「何とかライダーや、何とかレンジャーものに出てくる怪獣・怪人」だ。体肢カウントすると脊椎動物にも昆虫にも分類し難いモノが続出、「ゴジラ、アンギラス、モスラ、ガメラなどとは何か共存していけそうな感じがするが、昨今の怪獣たちには共存の手立を模索しようという考えが生まれてこない」と嘆き節で、番組制作側に、ちょっと教えて差し上げたい! なんというシュールさ、これだから読書はやめられない。
しかし本書、医学生ならぬ図書館員として、日々医学書と格闘する筆者にはありがたい本だった。神経内科がどんな診療をしているか、しみじみと理解できたからである。呆れられそうだが、内科・外科や放射線科、皮膚科小児科泌尿器科などといった科と違って「神経内科」は、咄嗟に掴み難かった。先生ご自身、冒頭で「若い頃に仲間内で神経内科はどのような科と説明すればよいか議論した」と書かれている。この前書きには「神経内科は脳と脊髄と末梢神経と、筋肉の病気を扱っていて、全身のなかで神経内科と関係ないのは骨の中身と血液ぐらい」とズバリ書かれていて、うーん、腑に落ちた、というのはこんな感じのことを言うのだろうか、印象的でございました。
本書は、臨床現場だけでなく、日常生活にも発生するさまざまな観察とその考察の乱れ撃ちである。観察対象は、這い這いを始めたお孫さんから師宣の『見返り美人』、ボクシングの世界タイトルマッチのポスターまで、もう何でもこい。文学作品さえも、片頭痛患者だった芥川龍之介の『歯車』に登場する描写を「片頭痛発作の前兆としての閃輝暗点の完璧な記載」と絶賛するなど守備範囲だ。これと、英国の天文学者エアリーが自身の閃輝暗点の時間経過を分析した論文を「彼らは、それぞれ自らの発作を、自らの専門領域で創作として発表した」と讃えていた。
エピソードはいちいちわかりやすく、体の仕組みや進化の過程について詳しいため、理由づけがあって印象にも残りやすい。筆者は肩こりや椎間板ヘルニア、手根管症候群などのメカニズムを具体的に理解できただけでも大満足である(そして肩こりの著者オリジナル予防策を実践中)。臨床医であるからこその、この臨場感。そしてそれを文章に起こす巧みさ。こうして一般書として文章化されなければ、これら貴重な経験は、我々の元には届かなかった。
そう、文章化すなわち言語化。本書読後のもうひとつの感想は、その「言語化」の重要性である。抽象的な事柄の言語化は難しい。「痛みだけは、あらゆる診療科に共通の症状である」と著者は言う。神経内科にもたびたび持ち込まれる「痛み」「痺れ」などの症状だが、これは言ってみれば自己申告なのである。どこが、どんなときに、どんなふうに、どれくらい痛いか、痺れるかを、患者はできるだけ正確に伝える必要がある。その痛みが果たして整形外科向きなのか神経内科なのか、脳外科なのか、判断がつき難い症状がたくさんあるのだ。だが患者によってその表現方法、表現力はまちまちだろうし、その読解においては医師側にもさらに工夫の余地があるのかもしれない。
本書はそれを読者に実感させる力がある。この功績は、きっと大きい。
うーん、患者も心してかからなければ。何といっても自分の体なのだから。少なくとも「正確に症状を伝える難しさ」は覚悟しておくべきで、その意識があればまた違うはずで、そう自分に強く言い聞かせてしまったこと、それが強烈に心に残ったのだった。
図書館 司書 関口裕子