「この一冊」 図書のご紹介


- 大学案内 About us
- 学部・大学院 Faculty Guide
-
入試情報
Exam Guide
- 大学機関 施設 University facilities
- 研究・産官学連携 Research and collaboration
- 学生生活 Student life
- 社会貢献・連携 Social Contribution and Cooperation
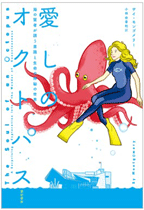
愛しのオクトパス 海の賢者が誘う意識と生命の神秘の世界
サイ・モンゴメリー (株式会社 亜紀書房 2017年)
2017/07/13更新201706号
著者は、昔からモンスター系が好きだったという。「あんな状況じゃゴジラが不機嫌なのは当たり前!」と思い、応援する側だったそうだ。
欧米圏では、巨大イカ・タコは恐怖の対象と相場が決まっている。ある意味、挑戦的な一冊だ。これはタコの生態を描くというより、タコと人間の邂逅について綴った本である。動物をむやみに擬人化するのはタブーであるのも承知の上での確信犯。のっけから、タコと文字通り「触れ合う」場面が展開し度肝を抜かれた。
アテナというミズダコは、水槽からにじり出るようにして著者を迎えた。
2歳半で体長150センチ、体重18キロの彼女は未知の人物との出会いに興奮し真っ赤になって「腕」をのばす。そして何十個もの吸盤を著者の腕に這わせて探ってきた。
うーん、筆者は正直、おののいた。だがこの場面を「エイリアンにキスされている感じがした」と描写したのには参った。アテナはまっすぐに著者を見つめてきたそうだ。
思い出したのは映画『E.T.』だった。
あれも公開当時、E.T.の容姿(?)について微妙な感想が飛び交ったものだ。主人公のエリオット少年はハーシーのチョコレートを撒いてE.T.を誘い出そうとし、E.T.はそれを拾い集め、交流が始まる。
筆者も当欄を担当するうちに、犬猫ペンギンハダカデバネズミ蜜蜂ヤマネ猛禽類ヒドラモグラ亀ヒヒ狼インコとありとあらゆる生き物について読んできたが(4年前の今頃はイカだった)、それにしてもタコの能力というか、生態については魅せられた。体の3分の2のニューロンは腕にあり、それぞれの腕は別個作業が可能である(作中でも、背後で悪さをするタコが登場する)。そのマルチタスクぶりはハンパなく、どういう回路なのか研究者にも未知の領域で、まるで『ガンダム』に登場するエルメスのビットみたいだ。1600個もある吸盤は、1つで10キロ以上の重さを持ち上げられ、嗅覚も味覚もある。道具も使う。半球を二つねじり合わせたボールに入れた食べ物を、開けて食べたあとご丁寧に閉めてよこす。水中で瓶に水を噴射させクルクル回すなど、ひとり遊びもする。彼らと飼育員や研究者との知恵比べが見ものだ。「利口な生き物を退屈させると始末におえない」という著者の呟きがおかしくてならない。
『インコの謎』でも鳥類について同様に書かれていたが、例えば脳の大きさで能力は判断できないのである。人間と生態そのものが違うのだと思い知らされる。擬人化はダメというセオリーについても、論文を書くためタコに通し番号をつけていた研究者達が、いつの間にか名前をつけて呼び始めてしまう下りで、考えさせられてしまった。
体表や吸盤の色の変化で感情表現もするタコ達(“表現力がありすぎる”とな)と触れ合ううちに、著者が「タコが自分をどう見ているか」にまで思いを馳せるのが印象的だ。簡単にだし抜けるので「頭悪すぎると思われているだろう」と苦笑いするのだ。他者に対し、相手本位に考えてみることは相互理解への第一歩ではないか。
実は作中でも『E.T.』について言及があったのだが『E.T.』のThe Extra-Terrestrial というのは「地球外生命体」というような意味である。Terrestrialには「地上の」という意味もあるので、水中でしか生きられないタコもまたE.T.といえそうだ。映画『メッセージ』に登場するエイリアンもタコ型だった。神経科学者によれば「脊椎動物以外では頭足類だけが、複雑で聡明な脳の成り立ちを示す唯一の例」だそうだ。
本書はまた、水族館という舞台に集まる「背骨のある皆さんと背骨のない皆さん」の物語でもある。ここが自分の居場所と集うさまざまな人々。夢を見るデンキウナギや、人懐っこいアオウミガメ(彼のフェイスブックは大人気)、膝枕でとぐろを巻くアナコンダなど、タコ以外の生き物たち。悲しい場面もあるが、喜びの直後に訪れた悲劇に対し「それでも昨日は完璧だった。たとえ死でも、その昨日を消し去るわけじゃない」という高校生ボランティアの言葉がつよく心に残った。
タコにぜひ触りたい、とは今のところ思わないけれど。
でも実際にタコと触れ合うチャンスが訪れたら断れるか、自信がなくなってきた。
それはちょっとした「チェンジ!」になるだろうと、もうわかってしまったからである。これほどの一冊を読んで、そう思わないわけにはいかないじゃないか。
図書館 司書 関口裕子








