「この一冊」 図書のご紹介


- 大学案内 About us
- 学部・大学院 Faculty Guide
-
入試情報
Exam Guide
- 大学機関 施設 University facilities
- 研究・産官学連携 Research and collaboration
- 学生生活 Student life
- 社会貢献・連携 Social Contribution and Cooperation
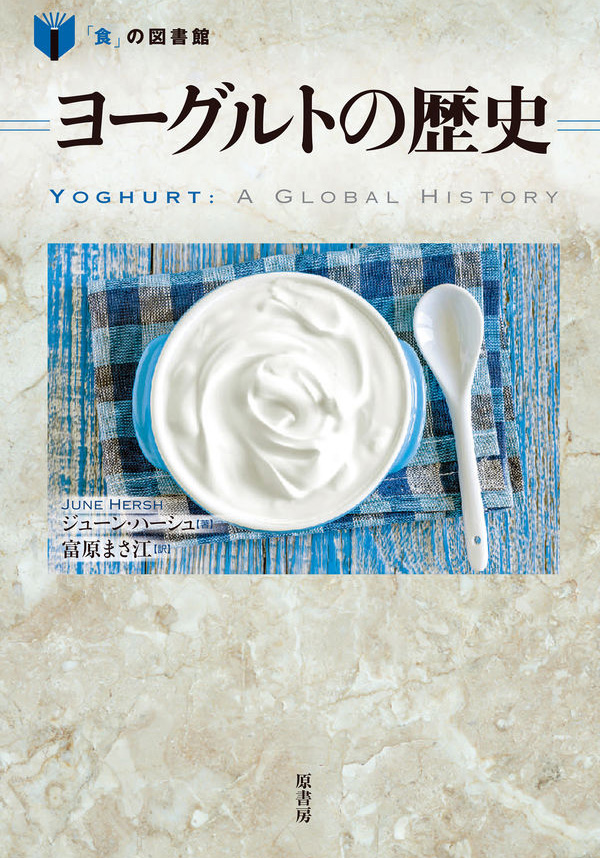
『食』の図書館 ヨーグルトの歴史
ジューン・ハーシュ 著・富原まさ江 訳(2021年 株式会社原書房)2022/05/30更新 202204号
「発酵」は多様すぎる。
パンやお茶やお酒、乳製品、大豆や魚・肉の加工品と種類多数。それらがそれぞれの地域で独自の発展を遂げていく。毎度ほとほと感心してしまう。
ではなぜ今回、この「ヨーグルト特化本」を選んだか。
ヨーグルトはおそらくいま、もっとも「健康」と関連して語られているからだ。
本書によれば、ヨーグルトと腸内細菌叢の関わりについて、2018年だけで4900本以上の論文があるということだ。わかる。腸周辺はホットだ。「腸内細菌」「脳腸相関」などをタイトルに頂く本は当館でも増えるいっぽうだ。
だが発酵が健康に及ぼすプラスの影響は、なにもヨーグルトに限らないわけで、では何がヨーグルトをそれほどまでチートたらしめているのか。
まずアルコールと違い年齢層を問わないし、カフェインなど中毒性もない。乳糖不耐症も突破でき、栄養は豊富だ。塩分や糖分や脂肪分を控えめにして健康食として摂取もできるが、スイーツとして楽しむのも全然ありだ。
何より摂取が簡単なのだ。コンビニにも売っている。価格もそれほどは高くない。
料理や(なんなら美容にも)アレンジ可で、凍らせてよし、飲んでよし。
時間がないビジネス旅行でもスーパーに飛び込み、乳製品のありそうなコーナーを探せばいい。海外でも語学は不要そうだ。ホテルの朝食で日本では見かけないブランドと出会う可能性もある。フランスや中国の瓶いりのやつは空き瓶もかわいい。
ヨーグルト好き迷宮にはまり、その先の扉を開けばヤギ乳やヒツジ乳のヨーグルトなどが待っている。最近は植物由来という新手も要注目だ。
さらにさらに、本書によればアメリカの冷凍食品コーナーには、犬用フローズンヨーグルトが並んでいるらしい。暑い日の水分補給にいいそうだ。
考えるほどに、ヨーグルトの立ち位置に立てるライバルは多くない。
そこに「腸活にいいらしい」というお墨付きまで次々でてくれば、無敵ではないか。
そして思うのだが、ヨーグルトって、大量生産がマイナスとして語られないのである。
本書にもダノンやネスレといった、巨大企業の歴史が語られている。どこも種菌を厳選し、開発も怠らず、健康との関係の研究をし続けている。
世界にはヴィーリ(フィンランド)やスキール(アイスランド)、リャジェンカ(ウクライナ)、ダヒ(インドやパキスタンなど)などなど、さまざまなヨーグルト系食品があるが、検索するとそれぞれ「乳製品だなー」という雰囲気の市販品パッケージがでてくる。やはりみんな、手軽に摂りたいという思いに変わりはないのだ。
あぁ。気軽に海外旅行に行けた時代に、もっと地元の乳製品を漁ればよかった。
筆者はフローズンヨーグルトに詳しくなかったので、本書を見て「これは食べねば」と思い立った。また、ヤクルトがこれほどのグローバル企業であることを実感しておらず、読後にヤクルト社のホームページを見て仰天した。台湾や香港、ブラジルなどへの進出には半世紀以上の歴史があり、ヨーロッパにも続々展開、最近では中東にも進出しているのだ。
代田稔とラクトバチルス・カゼイ・シロタ株についてもばっちり記述があった。
ところどころアレ?そうなの?な記述もあった。日本についても、抹茶や柿のフレーバーヨーグルトが漆器をイメージしたパッケージで売られているとあるが、そうなのか?ご存じの方がおられたら教えてください。
ともあれ、巻末にはレシピ集もあり、各国の食の写真も豊富で楽しい一冊だ。原書房さんは“「食」の図書館“と銘打ったシリーズで、トマトやダンプリング、ハチミツなどを取り上げている。また「お菓子の図書館」というシリーズもあってアイスクリームやパイの歴史物語がある。どれも楽しく時に意外で、何より美味しそうで、そしてまた旅に出たくなってしまう、罪作りな本たちである。








