はたらく人びと


- 大学案内 About us
- 学部・大学院 Faculty Guide
-
入試情報
Exam Guide
- 大学機関 施設 University facilities
- 研究・産官学連携 Research and collaboration
- 学生生活 Student life
- 社会貢献・連携 Social Contribution and Cooperation
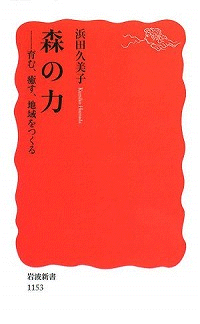
森の力
-育む、癒す、地域をつくる-
浜田久美子 (岩波新書1153 2008年)
2009/8/6更新 018号
なりゆきから「林業」に就職してしまった男子の物語である。
気の毒になぁ、というような「ひょんなきっかけ」から林業界に放り込まれた彼。
しかし、明日こそ逃げ出してやる、と呪文のように唱えながら、彼は少しずつその「なあなあ日常」に馴染んでいく…。
なんとも爽やかな青春小説だが、読んで思った。会社員より、例えば本当は林業に向いている人は、実はもっといるのだ。自分で知らないだけで。
さて、こちらの新書は「森」を舞台に、今、どんな動きが起こっているかを切り取った一冊である。「森」がクローズアップされる風潮を捉えて、本書の著者は言う。
「本当に森が必要不可欠で、それを十分に保ちたいと思うのならば、今、私たち人間の側の力量を上げなければならないと思う」
そして本書に記されたのは、森を身近に育つということ、森林とともに地域で豊かに暮らすということ、森のビジネスチャンス、森の職人、という4点。
どれも切り口が新しい。そしてどれも、収益や継続性を綿密に考慮した、社会的な動きである。これは将来、林業を目指す人のためだけの本ではない。例えば「森の“聞き書き甲子園”」という言葉をご存知だろうか。高校生が職人と交流しながら生き生きと自ら綴るこのイベントは、教職を志す人には興味深いと思う。また、バイオマス関連の会社について知りたいなら、本書がその出発点になるだろう。
知らないということは、チャンスを失うことでもある。
ならば、新書は格好の入門書だ。








