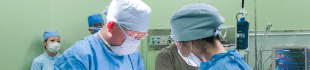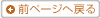学生からのレポート Report


- 大学案内 About us
- 学部・大学院 Faculty Guide
-
入試情報
Exam Guide
- 大学機関 施設 University facilities
- 研究・産官学連携 Research and collaboration
- 学生生活 Student life
- 社会貢献・連携 Social Contribution and Cooperation
食品セミナーⅠc レポート
「兎田ワイナリーでのインターンシップを終えて」

▲学生2名 兎田ワイナリーの前にて
4年次 五味 蒼馬
今回兎田ワイナリーさんのご協力により、普段できない貴重な経験を数多くさせていただきました。
初日は、秩父ブランの原料である甲斐ブランの収穫でした。実際にやってみると一列を終えるのに2~3時間かかりました。また、試食させていただいた甲斐ブランは甘くないサクランボのような味と強い渋みを感じました
二日目は、初日に収穫した甲斐ブランを使用して白ワインの製造を行いました。今回は白ワイン製造の主軸である破砕と圧搾を見学しました。機械を使って数十分で終了しました。圧搾では最初の2時間くらいは自重で先に果汁を出し、その後は機械内で風船が膨らみ圧力を利用し果汁を出す工程を見る事ができました。
三日目は秩父ルージュ(赤)の製造と市販品の試飲をさせてもらいました。赤ワインは発酵させてから圧搾をするので施設内は赤ワインの強い香りがしました。圧搾後に残ったブドウの果皮を味見させていただきましたが、ブドウ本来の味は全くなく、アルコールの香りと果皮に残ったタンニンの渋みを強く感じました。試飲で印象に残ったのは、ミズナラオークチップに浸漬させたワインと海中熟成したワインです。オークチップの方はウイスキーのような風味があり少し尖って感じました。しかし海中熟成をするとその尖りが削られ、まろやかに感じました。
三日間を総じていうなら、一本のワインを作るには結構な肉体労働と時間が必要であることが身に染みてわかりました。また、ワインの種類はたくさんありましたが風味や味に明確な違いがあることを実感できました。
4年次 豊田 雄大
今回のワイン製造実習では、収穫から仕込み、圧搾、テイスティングまで、ワインができるまでの一連の工程を体験することができました。実際に手を動かす中で、教科書では得られない現場の感覚や工夫を知ることができ、非常に貴重な経験となりました。
初日は強い日差しの下でブドウの収穫を行い、想像以上の体力を使う作業でした。特に印象的だったのは、ワイナリーの方々の収穫スピードの速さであり、経験と技術の差を肌で感じたことです。2日目は白ワイン用ブドウ「カイブラン」の破砕と除梗を行い、機械の利便性を感じる一方で、清掃や衛生管理に多くの手間がかかることを学びました。3日目には赤ワインの圧搾を体験し、皮ごと発酵させたブドウの強い香りに包まれ、まるでワインづくりの世界に入り込んだような感覚を味わいました。
最後のテイスティングでは、同じブドウ品種でも製法の違いによって味わいが大きく変化することを実感しました。本実習を通して、ワイン造りは単なる飲料の製造ではなく、農業・科学・文化が結びついた総合的な営みであることを改めて理解しました。今後もこの経験を糧に、食品製造の現場に対する理解をさらに深めていきたいです。

▲ワイン用ブドウの収穫①

▲ワイン用ブドウの収穫②

▲圧搾後のブドウ果皮
【「食品セミナーIc」シラバス概要】
- 社会で求められる実践力を養うため、大学外での経験を積み、学生自身が今後のキャリアについて考える機会とする。プログラムを受講し、担当者にレポートを提出し、単位認定を行う。
その他の企業へのインターンシップ(5日間)担当者:学年担任 様々な企業の業務に参加し、現場を体験する。 - 各業種で行われている業務の内容を学び,その業務の重要性や社会への貢献について説明できる。
- インターンシップ先での業務参加あるいは視察