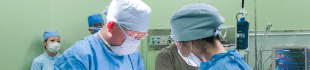動物行動福祉学教室 Research and faculty introduction


- 大学案内 About us
- 学部・大学院 Faculty Guide
-
入試情報
Exam Guide
- 大学機関 施設 University facilities
- 研究・産官学連携 Research and collaboration
- 学生生活 Student life
- 社会貢献・連携 Social Contribution and Cooperation
研究室紹介と研究内容
動物にとって少しでも快適な生活の提供や苦痛・苦悩の軽減を目指す研究を行っています。
適していない環境での生活は、動物に損傷の発生や免疫力の低下をもたらし、疾病感染リスクを高めることもあります。ヒトに飼育されている動物たちが肉体的にも精神的にも健康な状態で日々を過ごせる環境について探求します。そのためにも、行動学や生理学といった科学的視点から動物に対する理解を深めていきます。
教員紹介

- 氏 名戸澤 あきつ 准教授
- 学 位博士(農学)
- 専門分野動物福祉学、応用動物行動学
- 担当科目動物福祉・倫理論、動物資源科学概論、農場実習、卒業研究、など
Close-Up「研究」
- 1. 動物の生態や行動を理解する研究
-
動物にとって快適な生活を提供するためには動物の生態や本来の生活環境についてよく知り、理解しなければなりません。
ウシやブタといった産業動物は、遺伝育種されることによってその特性に変化が生じます。しかし、家畜化されていてもそれぞれの動物としての生得的な行動が備わっています。本来であればどのような行動がどの程度発現しているのか、どのような特性が備わっているのか、理解を深めています。
また、動物園や水族館で飼育されている動物の飼育環境は、本来の生息環境と様々な点で異なります。飼育環境では動物たちにどのような生活を提供するのが良いか、主に行動学的な観点から研究しています。
- 2. 動物福祉(アニマルウェルフェア)に関する現状把握および動物福祉向上を目指した飼育の検討
-
国内外問わず、動物福祉に配慮した動物の飼育や取扱いが求められるようになっています。
現場評価法による農場評価や聞き込み調査を実施して、国内における飼育の現状や動物福祉への取り組みを把握しています。現状を把握し、実際に取り組める問題解決策やより良い飼育方法について、現場の方たちと一緒に動物福祉の向上を目指します。
- 3. 動物とヒトの良好な関係性構築に関する研究
- 本来、動物にとってヒトは恐怖といった心理的ストレスを感じる存在といえます。しかし、畜産では給餌や搾乳といった日常的な作業や、予防・治療といった非日常の処置まで、様々な場面でヒトと動物が関わります。ヒトと動物が関わる場面で常に恐怖や苦悩を感じる状態は動物の心身の健康状態に影響します。また、動物が恐怖によりパニック状態になった場合、ヒトの方が怪我する可能性もあります。動物とヒトが良好な関係性を築けるようにするためにはどのような方策があるか検討していきます。
- 4. 動物にとっての良好な生活環境の提供に関する研究
- 飼育されている動物は、飼育場所の制限や、本来の生息環境と異なった気候や景観といった状況で日々を過ごすことになります。産業動物では、適切な飼育スペースの提供や温熱環境などの畜舎環境の整備が生産性向上につながることもあります。展示動物では、野生下とは大きく異なる環境の中で、可能な限り本能的な行動の発現を促したり刺激を与えることで良好な心身の健康状態をもたらします。このように、環境エンリッチメントに関する研究にも取り組んでいます。